|
平々凡々な高校生活で、
「すきです。先輩」 年下の男の子から告白される日がくるなんて、思ってもみませんでした。 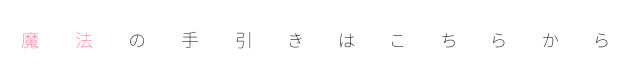 次の日かろうじて登校したわたしは、窓際の自分の席についてからもしばらく放心状態だった。口を開けぼけーと空中を見上げ、友達が不気味そうな視線をくれながら横を通り抜けていくのを視界の隅で捉えるだけ。緊急事態なのだ、許してほしい。 昨日の放課後、歌川くんに告白された。歌川くんというのは二個下の高校一年生で、ボーダー隊員でもありしかもA級の精鋭でとにかくすごい実力者らしい。この街の平和を守ってくれるボーダーの人たちへ感謝の気持ちを常日頃持っていたわたしは彼がボーダー隊員だと聞いたとき思わず拝んだものだ。それ以外にも歌川くんとはお話する機会が割とあったので、彼のことは色々知っている、つもりだった。けど。 バッと両手で頭を抱える。すかれてたなんて思ってもみなかった…!だってわたし初対面で結構アホっぽいこと言って歌川くんぽかんとさせた記憶あるし、普段話してるときもよく馬鹿やるし、間違ってもすかれるようなことした覚えまったくないよ。こんな、趣味も特技もなくて面白味のかけらもない人間を、歌川くんみたいな人がすきになるなんてそれこそ馬鹿な話、あるわけない。 そもそも本当に歌川くんはわたしをすきだと言ったのか?いや彼が人をおちょくるような人間だとは思ってないけど、もしかしたらわたしの記憶違いなんじゃないか、もしくは夢でも見てたんじゃないか。その可能性はまだある。早とちりは恥ずかしいぞ。 外から男の子の大声が耳に入ってくる。そちらに目を向けると、どうやらグラウンドではサッカーをやっているらしかった。古典の先生はとっくのとうに来てわたしのクラスの一限も始まっていたけれど、気にせず窓から体育の授業風景を眺めることにした。……そういえばあのとき、歌川くんもサッカーをしてたって言ってたなあ。 初めて歌川くんと会ったのは保健室だ。保健委員のわたしはその日昼休みの当番としてそこで時間を潰していた。保健室は空調が効いているのに加え、わたしの他には先生はおろか怪我人もいない閑散具合でとても心地よい空間だった。そんな憩いの時間は腕を派手に擦りむいた歌川くんによって終わりを告げたけれど、彼のまとう雰囲気は年齢の割に落ち着いたもので、ノックのあと静かに入室してきた彼を見ても不思議と嫌な気分にはならなかった。 歌川くんは友達とサッカーをしていたらしい。昼休みにサッカーをするなんてアクティブな人なんだなあと感心した記憶がある。彼はそれ以上は何も言わず手当を受け、ちょっとした雑談を交えたあとまたグラウンドへ戻っていった。後日、菊地原くんという彼のチームメイトの男の子から話を聞いたのだけど、歌川くんは一緒にサッカーをしていた男子生徒のミスを庇う形で怪我をしたんだそうだ。本気で謝る男の子とそれに手を振って保健室へ向かう歌川くんの姿を目撃したらしい。歌川くんは怪我の理由までかっこいい。 ジャージを羽織った男の子がシュートを決め、ゴールネットを揺らした。ホイッスルと共にグラウンドが沸き立つ。 (……ん?) よく見たら今決めたの歌川くんじゃないか?サッカーやってるのって歌川くんのクラスだったのか!立て続けにホイッスルが響き、どうやらミニゲームが終わったらしかった。白線で仕切られたフィールドから出て行く歌川くんをなんとなく目で追う。こちら側に向いて歩いてくるので、もしかしたら気付かれてしまうかもとさり気なく横目で見ることにする。 と、衝撃の光景が目に入りぎょっとする。最初は彼一人で歩いていたはずなのに、次々と周りに人が増えていくではないか。歌川くんが呼んでるわけじゃない。でも彼らはまるで魔法にかかったように、歌川くんの周りに集まっていくのだ。 思わず食い入るように見てしまう。すごい、歌川くんの人望がなせる技だ。まだ高校入学して半年くらいしか経ってないのに、もうあんなコミュニティの中心になってるんだ。すごい。 「ーよそ見かー。次の段落の現代語訳言ってみろー」 「え、は、はい」 知らない間に順番が回ってきたらしい。隣の友達に場所を教えてもらい、ノートをめくって読み上げる。「はい正解」予習はばっちりだ。周りで感嘆の声もあがる中、わたしは照れ臭くて肩をすくめた。 再び外に目を向けると歌川くんは男友達と固まり、わたしに背を向けて別チームの観戦をしていたので、やっぱりあれは夢だったんだろうと思い込むことにした。 音楽室の掃除が終わって教室に戻る途中で歌川くんと出くわしてしまった。別館二階の廊下でバッタリとだ。今月はわたしの音楽室当番と歌川くんの美術室の当番が被っている。なので終わる時間によっては鉢合わせるのだ。そもそも掃除だけじゃなく、歌川くんのクラスとわたしのクラスは移動教室の時間割とルートがたくさん重なっているからよく顔を合わせる。歌川くんの存在を認識したあと声を掛けられるようになって初めて気付いた。 「先輩」 「こ、こんにちはー…」 でも今は、会いたくなかったんだけどなあ…。 すっかり背の高い歌川くんに気圧されないよう距離を取ろうにも彼がスタスタと詰めてしまうので意味はない。昨日とまるで変わらない彼の態度に胆力という言葉を思い出して、いやあれは夢なんだと思い直していつも通り振る舞おうと背筋を伸ばすと、歌川くんは一メートルほど間をあけた場所で立ち止まり、わたしを見下ろして目をぱちくりさせた。 「返事聞かせてもらえるんですか?」 一撃で気まずさがメーターを振り切る。 「…………え、あの、…」 「ああいや、べつにいいですよ、いつでも。俺が言ったんですし」 そうだわたしの記憶にも確かに「返事はいつでもいいです」って言った歌川くんがいる。本当に、あれはわたしの記憶違いじゃなかったのか。夢じゃなかったのか。 本当に、歌川くんはわたしをすきなのか。 「なかったことにしないでさえくれれば」 本来恥ずかしいことを言ってるはずの歌川くんはしかし堂々としていて、わたしはめまいを覚える。しかも気のせいという理由で若干なかったことにしようとしていた節があるためどう返していいのかわからず、「はは…」と乾いた笑いを漏らしてしまった。それを肯定と受け取ったらしく、歌川くんの表情が少しだけ曇った。やばい、と背筋が凍る。 「あ、あの、ごめん、でもちゃんと考え、ます……」 「なんでそんな嫌そうなんですか」 苦笑いする歌川くんから目を逸らす。そうわたしは君とどうなるか考えるのが嫌だ。先のことを考えたらすぐに目の前が暗くなる。自己嫌悪で死にたくなる。ちょっと考えればわかることだ。 「歌川くんはわたしなんかと住む世界が違うからだよ…」 俯いてしまう。君が本当に今、わたしをすきだと思っていたとして、その気持ちに応えたら何が待っていると思う。わたしは間違いなくみじめな自分に苛まれることになる。「歌川くんはスポーツができて頭もよくてかっこよくて男友達には慕われてて女友達にはモテモテで、ボーダーではA級とかいう精鋭らしいし性格もよくて気配りができて礼儀正しくて、……そ、そういう人だからこの先、大学生とかになって環境が変わったら、歌川くんはわたしをすきになったことを後悔するきっかけがいくつもあるんだよ。だからわたしも、歌川くんをすきにならない方が身のため、なんです…」昨日出た結論だ。そこに辿り着いたから、なかったことだったらいいなと思った。こんなつまらない人間と歌川くんみたいなよく出来た人間が付き合いでもしたら、つまらない人間の方はきっとどうにかなってしまう。 「……先輩、俺のことすきなんですか?」 「ちがうよっ!……?」 咄嗟に否定して顔を上げると、歌川くんはなぜか口元を隠していた。眉間に力を入れ何かをこらえているようだ。いきなりどうして、と首をかしげたら、彼の耳が赤いのに気が付いた。ハッとする。 「て、照れてる…?」 「照れますよ。すきな人にほめられたら誰だって」 「あ、う……でも照れるの初めて見た」 「そうですか、結構照れてるんですけど」 じゃああまり顔に出ない体質なのかもしれない。それはうらやましい。歌川くんが隙を見せたことにより心の余裕ができたわたしは、眉をハの字にしてだけど、少しだけ笑うことができた。 「でも、脈がないわけじゃないみたいで、少しホッとしました」 「みゃ、脈って……わたし、歌川くんがわたしのことすきだって言わなかったら、こんなこと考えなかった、よ」 「それは俺の狙ったところです」 すぐに調子を取り戻したらしい歌川くんは手を元の位置に下げスラスラ述べる。意識してもらいたかったんです。先輩が俺のことまったく眼中にないのをなんとかしたかった。ただ話しかけるだけじゃ足りないと思いました。そんなことをいけしゃあしゃあと言えてしまう歌川くんにわたしは圧倒されるばかりだ。 歌川くんは話し上手だし聞き上手でもある男の子だ。歌川くんの話す友達やボーダーの話も楽しかったし、わたしの話も何でも聞いてくれるからいい人だなあと思っていた。歌川くんにとって絶対つまらないような話題でも嫌な顔せずうんうんと相槌を打ってくれて、要所要所でツッコミも入れてくれる。総じてコミュニケーション能力が高い人だ。しかも廊下で会うと決まって挨拶をしてくれるし、誰にでも親切でわたしなんかにも優しい。そういう、隙のない人だと思っていた。いや今でも十分思ってるんだけど、少なくとも、わたしの話を楽しそうに聞いてくれるのとか、わたしなんかにも優しいのとかは、違うんだ。全然気付かなかった。そう、本当にわたしは、昨日まで、歌川くんとこういうことになるなんて微塵も考えていなかったのだ。 視線がうようよ泳いでしまう。歌川くんの顔が見れない。頬はさっきから熱いし背中は変な汗をかいてる。 「先輩は、隙だらけに見えて実際は相手にしてない感じが、なんだかこっちを燃えさせますよね」 「そ、そんなつもりはなかったんだけど」 「自覚ないのが余計タチ悪い」 自信に満ちたまま、少しだけ笑った歌川くん。わたしは何て返したらいいのかわからなくて、反射的に笑ってしまう。ぎこちない笑顔だと思うけれど、人はどうしたらいいのかわからないとき笑ってしまう生き物なのだ。 「じゃあ、俺防衛任務あるので。……また」 「ま、またね…」 ひかえめに手を振って、歌川くんを見送ろうとする。けれど歌川くんはそれにふっと笑う。「俺のこと持て余してるのにそうやって来る者拒まずなの、ありがたいですけど、他の男にも簡単にしないでくださいね」そんなことをサラッと言って、本当に背中を向けて教室へ戻っていく。それを半ば呆然と見ていた。 きっとまもなくだ。わたしは歌川くんをすきになる。ならないわけがなかったのだ、あんな人に目をつけられたら最後、何もなかったなんてできない。その証拠に、歌川くんが「また」話してくれることをこんなに嬉しいと思ってる。ぜんぶ君の思うツボだった。 手当てが済むと最後に受付のカードを書いて終わりになるらしい。目の前の保健委員の人はそれを挟んだボードを抱えながら、ボールペンで必要な項目を埋めていた。 肘から手にかけて大きく擦りむいた傷口は女の先輩によって丁寧な処置を施され、今はほとんど被覆材の張ったような違和感だけになっていた。気を遣わせるのは悪いからあまり目立たないようにしたかったのだが、これは仕方ないか。今の季節では暑いがグラウンドに戻ったらジャージを羽織ろうと考える。「お名前は?」歌川遼ですと答えれば、うたにかわ?と聞かれる。それでわかるのかと思いつつ頷くと、彼女は再びボールペンを動かした。 「りょうってどういう字書くの?」 「しんにょうに…」 「あ、わかった。こうだ」 見せられたカードには正しい漢字で歌川遼と書き記されていた。下手でも綺麗でもない字だった。そうですと頷くと、「かっこかわいい名前だ」ボードをそばのデスクに置きながら反応しづらいことを言うので、はあ、と下手な返答をしてしまう。 「はにかみ王子だねー」 思わずぽかんとしてしまう。それを見た彼女もぽかんとして、それから途端に慌てだした。「あっあの、はにかみ王子というのは、」そこでようやく俺は、テレビで聞いたことのある愛称だと思い出し得心した。「いや、わかりますよ」フォローするようにそう返すと彼女は目をぱちぱちと瞬かせたあと、照れ臭そうに笑った。どちらかというとあなたの方がはにかんでる、と思った。さすがにそれは口にはしなかったが。 「あ、も、もう行っていいですよ」 「……はい。ありがとうございました」 「いーえ」 居た堪れなさそうに肩をすくめる彼女に立ち上がったあと軽くお辞儀をする。そばのデスクに目をやると、そこに置かれたカードの担当者欄にはという名前があった。 「……じゃあ、また」 「? またー」 ひらひらと手を振る先輩の声を背に保健室を出る。きっとあの人は今、深く考えないで返しただけだ。かくいう俺自身も深くは考えていなかったのだが、なんとなく、「また」があったらいいと思った。
>>「そして心のどこか」
|