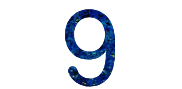

お昼に待ち合わせて駅近くのレストランで食べたあと、駅に併設されてるデパートを目的もなくぶらぶらしていたら、嵐山くんのお家に着く頃には夕方の五時を過ぎていた。いらないと遠慮する嵐山くんの制止を振り切って買った菓子折を玄関に入ってすぐ嵐山くんに渡すという間抜けな通過儀礼を行ったあと、一緒に住んでるという嵐山くんのおばあさんに挨拶をした。それからリビングに通され、ダイニングテーブルのイスに腰を下ろす。六人用の大きなそれは廊下を繋ぐドアの正面に置かれており、テレビと向かい合ったローテーブルとソファも見えた。他にもマッサージチェアやバランスボールが目に付いたけれど、それでも窮屈な印象を受けないくらい広い空間だった。三世帯住宅のお家は初めて入ったので相場はわからないが、少なくともわたしの家より間違いなく大きい。
「何か珍しいものでもあったか?」
「あ、いや、違うんだけど」
声をかけられ思わず肩をすくめる。キッチンからアイスティーをグラスに入れて持ってきた嵐山くんはテーブルにそれを二つ置くと、向かいのイスに腰掛けた。先ほどアイスティーでいいかと問われて二つ返事で頷いたけれど、そもそも常時アイスティーがある家なのか、嵐山家は。いただきますと両手で持ち上げ、一口含む。目だけで左を見ると窓の外は夕闇が深くなっていた。ついさっきまで明るかったのに、もう十一月にもなると日が短くて仕方ない。
と、リビングにチャイムの音が響いた。さきほど見回した際見つけていたインターホンへ目を滑らせると、そのモニターには薄手のコートを着た髪の長い女の子が映っていた。
「桐絵?」
嵐山くんの呟いた声にどきっとした。その心臓に人知れず驚いてる間に嵐山くんは席を立つ。インターホンのボタンを押し、画面越しの彼女に「待ってろ、今開ける」と声をかけてから、、悪いな、とわたしに断りを入れてリビングを出て行った。
…どきっとしたのは、嵐山くんが女の子のことを名前で呼んだからだろう。キリエって呼称は多分下の名前だ。珍しい苗字の可能性もあるといえばあるけど、彼の内包する言葉には親しさがうかがえた。モニターは消されもう彼女の顔は見えない。顔立ちは大人っぽかった気がするけど、なにぶんモニター越しだ。はっきりとは言えない。
「どうした、桐絵?」
「おばさんに渡してって頼まれたの。もう帰ってる?」
「まだなんだ。そろそろだろうし上がってくか?」
玄関から聞こえた声にぎょっとしてしまう。ま、まじか!途端に姿勢を伸ばして居住まいを正してみる。キリエさんが愛嬌のある明るい声で「せっかく来たしそうしようかしら」と特に迷うことなく返答したことによって一気に緊張が走る。玄関の扉が閉まる音。二人分の気配。どうしよう、わたしどんな顔すればいいんだ、というかキリエさんは嵐山くんとどういう関係、「今が来てるんだ」え?
「え?」
わたしの心の声が漏れたのかと思った。けれどそれは違った。キリエさんの声だった。玄関から聞こえてきたその声がしてすぐ、嵐山くんと、彼に促されて続いて入り口に姿を現した、女の子が見えた。
「…え、えっと」
明るいオレンジのロングヘア、前髪も左右に分けて流していて、嵐山くんとの身長差のせいか、モニターでの印象より幼く見える。けれどよく見ると顔立ちは大人びているので、同い年くらいかもしれない。
なんて言えばいいのかわからず身を縮めてどもるわたしに対し、堂々とした態度のキリエさんはしかし驚いているようだった。目を大きく開きわたしを凝視する彼女から逸らす。な、なんかごめんなさい…。
「、こっちはいとこで、高校二年の小南桐絵だ」
「あ、いとこさん、なのか…」
「ああ。で、桐絵、だ。前に話しただろう」
「…准…」
何か言いたげな声音だった。とっさに顔を上げると嵐山くんは桐絵さんに笑って首を傾けていて、「桐絵もアイスティーでいいか?」と言いながらキッチンへ向かった。桐絵さんの表情は嵐山くんに隠れて見えなかった。キッチンへ消える嵐山くんを目で追う。
「…大丈夫。あとで自分でやるわ」
その声はさっき初めて彼女の声を聞いたときと同じような音だった。それにしても、可愛い声の女の子もいたもんだと半ば感心したように再度彼女を見やると、桐絵さんは長いまつげを瞬かせ嵐山くんを見ていた。その悲しげな表情に、わたしは昼ドラというワードを思いついて、もしかして彼女は誤解をしているのではないかと首を縮こめた。
「あの、桐絵さん、」
「え?」
「嵐山くんとはあの、ただの友達で…」
「知ってるわ。…准から聞いたから」
「そ、そうですか」
いとこの桐絵さんは密かに嵐山くんに片思いをしてて、いきなり現れたポッと出の女に彼を取られるんじゃないかと勘繰ってる、と思ったけど、どうやら勘繰ってたのはわたしの方だったようだ。彼女は一度目を伏せ、それからパッと顔を上げて、「それよりなんでさん付けで呼ぶの?わたしの方が年下なのに」と笑って肩をすくめてみせた。
「え、じゃあ、…桐絵ちゃん?」
「すきに呼んで構わないわ。さん、准に呼ばれて来たんでしょ?」
その質問にはどう答えていいのか迷ってしまった。頷くには「呼ばれて来た」のニュアンスが違う気がする。嵐山くんの家に来たのは誘われたからなので、そういう意味では桐絵ちゃんの予想は正しい。けど、ここに一人で出向いたわけじゃなくてさっきまで外で二人でいてそのあと来たから、そういう意味だと呼ばれて来てはいない。でもかといってご丁寧にお昼の駅集合から話すのもくどいかなと逡巡していると、キッチンからは桐絵ちゃんのアイスティーの代わりにお菓子の盛り合わせが入ったバスケットを運んできた嵐山くんが戻ってきた。
「そうだよ。副と佐補に会わせたくてな」
「その肝心の二人はどこなの?」
「上にいると思う。部屋の電気はついてたし靴はあるから」
「じゃあ呼んできてあげる」
「ほんとか、頼む。なら三人の飲み物準備しとくな」
テーブルにバスケットを置いてまたキッチンへ向かう嵐山くんを目だけで見送る。ワンテンポ遅れて、ええ、と返した桐絵ちゃんの方を見ると彼女はすでに踵を返していて、廊下を出てすぐ右の階段を上って行った。何か意味深な、視線を受け取っていた…気がするのだけど、勘違いかもしれない。でもそれにしては何か考え込んでるようだった。これも気のせいかな。人の頭の中を考えるのは難しい。初対面の人なんだからなおさらだ。
嵐山くん曰く、下が騒がしければ降りてくると踏んで弟さんたちを呼びには行かなかったらしい。年頃だからか距離感が難しくてなあ、と自嘲気味に零す彼に苦笑いする。今まで話を聞いてきた限り、嵐山くんはかなり兄弟愛が大きい。溺愛なのだ。それでいて立派な人だ。もしわたしに嵐山くんみたいな兄がいたら、圧倒的な偉大さを誇る彼が自分たちに甘いという事実は、かなりむず痒いかもしれない。
話をしている間も嵐山くんはキッチンで飲み物を注いでいる。キッチンとリビングは繋がっているので全然話せる距離だ。つまり先ほどの桐絵ちゃんとの会話も聞こえていたはず。嵐山くんからしたら微妙な内容だっただろう、と思い、グラスを三つ運んできた彼に弁明することにした。
「さっき桐絵ちゃんと話してたことなんだけど、あれは桐絵ちゃんが嵐山くんをすきで、わたしの存在を快く思ってないんじゃないかと思ったからなので…」
「はは!なんだそれ。そんなこと思ってたのか」
「いやー深読みしてしまった…」
あははと頭を掻くと嵐山くんもおかしそうに、「それであんな申告したのか」と笑った。
「だってちゃんと言っとかないと可哀想と思って」
「…まあそうだったのかもしれないけどな…」
眉尻を下げて苦笑いをした嵐山くんの台詞はまだ続きそうだったけれど、遮るように二階からタンタンタンと小刻みに足音が聞こえてきたので会話は中断された。足音は複数ある。
降りてきたのは予想通り中学生くらいの女の子と男の子で、一目見て、あ、嵐山くんの妹さんと弟くんだ、と思った。なんたってふわふわの黒い髪の毛が嵐山くんと同じなのだ。これは同じ遺伝子を受け継いでる証拠だろう。
「お、来たな!」
「兄ちゃんの友達って?迅さんじゃなくて?」
「ばっか桐絵ちゃんが女の人って言ったじゃん!」
妹さんの方がお姉さんというのも本当らしく、弟くんの腕をドンと肘打ちしていた。座りっぱなしも居た堪れないのでわたしも立ち上がり彼らの方へ近付く。普段着の彼らはわたしと目が合うなりおお、とよくわからないリアクションをして身を寄せ合った。それから嵐山くんの自己紹介ならぬ他己紹介の末、彼らと知り合うことができたのだった。
それからは五人でダイニングテーブルのイスに座りいろいろ話していた。嵐山くんが二人を可愛がっているのがよくわかり、微笑ましい気持ちになったものだ。
それを見ていてなんとなく、嵐山くんがわたしに過保護な一面を見せるのは、佐補ちゃんたちに向けるそれと同じ感じなのかな?と思った。いとこの桐絵ちゃんはボーダーらしいから仕方ないとはいえ、中学二年生の子たちと同レベルで心配されるわたしって一体。いやそもそも嵐山くんと友達になれたきっかけが佐補ちゃんとお揃いの定期入れだったわけだし、嵐山くんの中でそのポジションと同一視するのも頷ける、のかもしれない。大学生として情けなすぎて頷きたくないが。
そんな和気あいあいとした会話の最中、嵐山くんがトイレに席を立った。一旦話が途切れ、隣り合った副くんと佐補ちゃんが目配せしたのに気付いた。佐補ちゃんが副くんを肘でつつく。すると、渋るように顔をしかめたあと、意を決して副くんがわたしへ身を乗り出したではないか。
「さん、兄ちゃんの彼女なの?」
「……まさか!」
予想外すぎる質問に間抜けた返答をしてしまう。ほら嵐山くん、はたから見るとそう思われるんですよ。
|