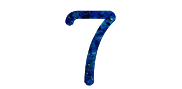
実は友人にはまだ、嵐山くんと友達になったことは言ってなかったりする。やばいかなと思いつつ嵐山くんと知り合ってから四人の中の話題として大盛り上がりはしてないからいいかなと思ってる次第である。もしかしたらわたしがいないときに盛り上がってるって可能性はなきにしもあらずなのだが、それは神と友人のみぞ知る、である。
なにぶんわたしたちはそのときそのときで講義が被ってるメンバーだけが集まるという成り行きなスタンスなので、行動するメンツは入れ替わり立ち替わりといった感じなのだ。そのため四人が綺麗に揃うお昼は火曜だけだ。
もしそのとき嵐山くんのことで盛り上がることがあったら言おうと思ってる。という決意はしてるのに罪悪感にはそれなりに襲われてるので、早く言った方がいい気もしてる。
でも、なんていうか、わたしの友達の嵐山くんはみんなが期待してる嵐山准じゃない気がするんだよなあ……いや彼の人柄が期待はずれとかってわけじゃないんだけど。有名人の嵐山准っていうより、わたしの友達の一人、みたいな…そんな考えも馴れ馴れしすぎるのかな。そんな思考を巡らしては腑に落ちないまま、わたしは机に置いた真っ暗な画面のままの携帯とにらめっこしていた。
「」
「…おー嵐山くん」
後ろの教室のドアから入ってきたらしい嵐山くんが軽く手を挙げた。ここの大教室の机は横長で八人用となっている。奥いいか?と問うた嵐山くんに二つ返事で頷き、通路側の席に座っていたわたしは一度外に出た。嵐山くんはその列に入りわたしの荷物を挟んで一つ開けた奥の席へ行く。カバンを机に置いた嵐山くんと、わたしが再び折りたたみ式の座面を出し腰掛けたのはほとんど同時だった。
「ほんとに会えたな。というか待たせたか?」
「そこまでじゃないよ」
「でも出ていく他の学生ほとんどいないぞ。悪いな」
「全然!ほら、わたし時間あるし」
今回珍しく食堂以外で嵐山くんとエンカウントしたのは、なにも偶然ではなく二人によるれっきとした意図的な計画だった。このあいだ話している最中、月曜のわたしの四限の教室と嵐山くんの五限の教室が同じなことが判明した。授業中、スクリーンに映し出すプロジェクターが故障した話をしたところ五限でいつもスクリーンを使う教授が黒板で代用していたことを彼に聞き、もしや、となったのだ。
そしたらどちらともなく、じゃあそこで会えるかもねという話になり、今週試してみることにしたのだ。実は四限の先生はいつも定刻の五分前に授業を終えるので、学生が教室を出るのも早い。五限の嵐山くんとこれまで一度も会わなかったのはそれが理由だと思う。今周りに出て行く生徒がいないのもそのせいだ。嵐山くんも別の授業から急いで来てくれたのだろう。待ったのは正味八分くらいだろうか。ちなみにわたしは月曜は四限までなので、このあとは帰るだけなのだ。荷物は整え終わっている。
「まあ、わかってたけど…会えたところですぐ授業だな」
「ふっ…そうだね」
呆気ないオチに吹き出してしまう。教室内にはぞろぞろと講義を受けるべく入室してくる学生が増えてきていた。嵐山くんも眉を下げながらバッグの中からルーズリーフや筆箱を出していく。あと五分もしたら五限が始まるのだ。食堂では会えるかも!楽しそう!って盛り上がってたわたしたちだったけど、実際は入れ違いのような慌ただしいものに近かった。
いやはや、しかしながら…。にやっと笑ってしまう。
「わたし的には悪くない」
「……」
こちらに向いてきょとんとした顔。それが、じわりと緩んでいく。
「俺も」
堪えきれずといったような笑みだ。同じこと思った。それにわたしも満足する。
「…そうだ。、来週の土曜空いてないか?」
「どうして?」
「久しぶりの休日でさ、どこか出かけるのに付き合ってほしいんだ。それとがよければ、弟と妹にも会ってほしい」
「おお…」
予想外のお誘いに内心たじろぐ。まるで親密な間柄じゃないか。しかも弟と妹ってことは、お家に行くってことだろうか?すごい、な。
「暇だけど、わたしなんかでいいの?」
「もちろん。駅前とかぶらぶらしたい」
子供みたいに楽しそうに笑う嵐山くんに肩の力は抜け、ほっと息をつく。「じゃあぜひとも」答えると、嵐山くんは一層笑みを深めた。テレビで見る嵐山准て、同い年とは思えないすごく大人な男の人って感じがするけど、本物の嵐山くんはそれよりもっと幼くて、年相応だ。子供みたいな笑顔は初めて見た。久しぶりってどれくらいぶりなんだろう。毎日暇を持て余すかバイトをしてるだけのわたしなんかには到底想像もつかないハードな日々を送っているはずだから、聞いてもピンとこないかもしれない。
そうだ、手帳に書いとこう。カバンから手帳を取り出し、今月のページを開く。来週ってことは十一月だ。一枚めくるも恐ろしく白いカレンダーが現れて虚しい気持ちになる。筆箱へとカバンの中へ手を伸ばそうとすると、「はい」横から嵐山くんの手がシャーペンを差し出した。気が利くなあ…!よっぽど感動しながらそれを受け取る。よく見たら胴体に入ったロゴから、テレビ局のものであることがわかった。わたしの考えてることに気付いたらしい嵐山くんが少し照れたように頬を掻いた。
「…ニュースに出るともらえる記念品なんだ」
「へー……ん?!まってめっちゃ書きやすい何これ」
[嵐山くんとお出かけ]なんと書きやすいことか。サラサラいけた。軽いし持ちやすいし、試しに頭をノックしてみたら押し加減もいい。心なしかいつもより綺麗に字が書けた気さえする。このシャーペンは神さまか…?!と思わずにはいられないレベルだ。嵐山くんも途端に「だろう?!」と目を輝かす。
「書き心地がよくて愛用してるんだ!」
「最高だよテレビ局グッジョブ!いいな〜!」
大絶賛である。デザインはザ・記念品って感じだけど、見た目からではわからないなめらかな書き心地が備わっている。侮りがたし記念品…!両手で端っこを持って崇めるわたしに対し、嵐山くんはちょっと落ち着きを取り戻したようで、ごほんと咳払いをしてから言った。
「、気に入ったんならぜひもらってくれ」
「え?!でも悪い、」
「出るたびもらってるから家にまだあるんだ。消耗品でもないし、もらってくれるならむしろありがたいよ」
そ、そうなのか…?もしそうならこちらこそぜひとも頂戴したい。わたしの板書の第一線で活躍してほしい!その欲求に逆らえなかったのもあってわたしはいとも容易く、お言葉に甘えることに決めた。
「じゃあいただきます!ありがとー!」
「…いいえ」目を細めて笑った嵐山くんが、まるで慈愛に満ちた表情をしていた。よっぽどもらってほしかったのだろうか。理由はわからないけれど、彼の表情に悪い意味はないと思うのでわたしも笑い返すことができた。
すぐに前の入り口から教授らしき人物が入ってき、そのまま教壇に立った。五限の先生だ。わたしはシャーペンを片手に持ったまま、急いでカバンを肩にかけて席を立った。
「じゃあ帰るね、嵐山くん」
「今日は直帰か?」
「うん」
「そうか。…警戒区域には近づくんじゃないぞ」
彼の唐突な発言にポカンとしてしまう。まさかそんな注意をもらうとは思ってなかったのだ。久しぶりに言われたなあ…。
「…わかってるよー」
語尾にはてなマークが付きそうだったけど隠せたと思う。ごまかすように笑って、シャーペンありがとねと踵を返した。
お母さんやお父さんにも四年前から口を酸っぱくして言われてる。わたしは大規模侵攻のとき遠くにいたし家も東三門とは離れた場所にあるからか壊れず実害がなかったせいか、あんまり危機感がないらしいのだ。でもそれとこれとは話が違う。わたしはそんなに馬鹿じゃない。教室を出るなり立ち止まり、筆箱にシャーペンをしまう。べつに怒ってるわけじゃないけどさ。その証拠に、カバンを肩にかけ直してからは、さっきと同じ調子で歩き出した。
そりゃー、言われなくても行きませんよ。行く理由がないですもん。
|

