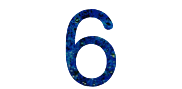
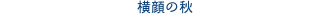
嵐山くんは食堂がすきなんだそうだ。それは周りのざわついた音が落ち着くとかイスの座り心地がいいとかご飯を食す場所としては関係ない部分に魅力を感じているのもあったけれど、一番大きな理由としてご飯がおいしいという点があった。賑やかな空間でぼっち飯という孤独感に酷くおびえるわたしと違い周りのことはあんまり気にならないタイプなのか、彼は一人行動もそれなりに好んでする人間らしかった。その証拠に読書や音楽も嗜むという彼は、すきなジャンルやアーティストを問うとスラスラといくつか挙げた。本当なのだ。べつに疑ってたわけじゃないけど、バッグから文庫本とウォークマンを取り出してみせてくれたときにへえ…と妙にしみじみ零してしまった。
だって嵐山准だ。三門市の有名人でテレビにも出てて、老若男女問わず人気の男の子だ。常に周りに人がいて、いうなればリアルが充実していそうな好青年。一人の趣味なんてなさそう、というか縁遠そうなイメージしかなかった。しかも文庫本のあらすじもすきなアーティストも、わたしでもとっつきやすそうな話だったり曲だったりで、身近に感じずにはいられない。文庫本をパラパラとページをめくった時点で興味を持ったことを見抜かれたのか、「読み終わったら貸そうか」とまで言われたのには驚いた(そして素直に予約した)。
一人の趣味を持つ嵐山くんは更にコミュニケーションの権化というべきか、本の話題だけでも相当話を膨らませる力を持っていた。聞き上手でもあるからわたしの話も楽しそうに聞いてくれて、こちらも気持ちよく話すことができる。オススメを聞かれた際、自分のすきなものしか答えられなかったわたしのレパートリーのなさには逆に笑えた。それでも嵐山くんは、話の流れで冗談交じりに「わたしも貸そうか」と聞いたのを、嬉しそうに頷いてくれたのだった。
(嵐山くんは、本当に偉大な人だなあ…)
本人を目の前にしてしみじみと思う。パクリとデミグラスソースのオムライスを口に入れる。うむ、美味しい。これで480円なのだから満足極まりない。ちなみに嵐山くんが食べてるのも同じものだ。何を隠そう、嵐山くんがオムライスにすると言ったのを聞いてわたしもそれにしたのだ。これがまた外れない。もともと食堂のご飯はおいしいと言っている嵐山くんの言葉と、選り好みの激しくない自分の味覚が合わさっているから大抵のものはおいしいと思うのだろうけど。少なくとも友達が前に言ってた、食堂のご飯はおいしくなさそうというのは単なる食わず嫌いだった。
こうして嵐山くんと食堂に来たのはこれが五回目だ。畏れ多さもさることながら、一人で昼食を摂っていた時間は今や嵐山くんとご飯を食べるのがいつもの流れとなっていた。といっても一週間で二回会ったのは今週と先々週だけで、先週は一度も会わなかったくらいだけれど。そういうムラっ気のある頻度で、主に昼休みの一時間だけ、こうして嵐山くんと会話をする時間が設けられていた。それももう一ヶ月になるのか、とふと気付いた。
まさか後期の大学が始まった初日で嵐山准と知り合えるなんて、いや、会えるなんて思ってなかったなあ。前期にしょっちゅう友達とぎゃーぎゃー騒いでたのが懐かしく思えるくらい、あっさりと、偶然に、三門市の有名人で同じ大学に通う嵐山准とファーストコンタクトを果たした。わたしが落とした定期を拾ってくれたのだ。なんと親切なことか。なんでもわたしのそれが妹さんと同じパスケースだったらしい。妹さんと同じ趣味してる大学生のわたしって、と微妙な心境に陥りつつ、聞けば中学二年生の双子の弟妹がいるということで興味は俄然そちらに向いた。男女の双子ってめずらしいって聞いたことある。嵐山くんの弟さん妹さんも一卵性双生児らしいからなおさらだ。
その次の日の二限終わりに校舎内で偶然再会したとき、食堂でご飯を食べないかと誘われた。一日ぶりの嵐山准に感動したわたしはあわあわと動揺しながらもお誘いにはちゃっかり乗じたので、図太い神経してるよなあと自分でも思う。
でも多分、その日辺りから、嵐山くんと仲良くしてると思う。ちょっと話してみてわかったのだが、嵐山くんはものすごく話しやすい男の子なのだ。そりゃーもう、驚いた。テレビの中で笑顔を輝かせている有名人とは思えないほど、気さくで、嫌味がなく、中身までイケメンだったのだ。初対面の時点では緊張していたはずのわたしもいつの間にか彼を目の前にして大笑いできてしまうほど取り繕うことなく気楽に話せて、一ヶ月経った今ではすでに、沈黙でも気まずいと思わないほど打ち解けられていた。
実のところわたしは大学に男友達がいなかったので、彼は唯一の存在として、ひっそりと、心の中に君臨しているのであった。
「ごちそうさまでした」
「んー」
やはり男の子なので食べるのも早い。口にチキンライスを詰めながら答えると、嵐山くんは揃えた手をお皿の脇に置きながら、眉をハの字に下げて笑った。
「待ってるよ」
咀嚼ののち嚥下。ごくんと喉を通ったチキンライスが食道へと消えていく感覚を覚えながら、トレーに置いていたステンレスボトルのお茶をごくごくと飲む。わたしのオムライスはあと四分の一ほど残っていた。ハンドタオルで軽く口を拭く。
「ごめんよ」
「いいよ」
ははっとおかしそうに笑う嵐山くんをじっと目に焼き付けてから、瞬きをする。前からずっと思っているのだけど、嵐山くんは本当に素敵な笑顔を見せる。わたしの心のフォルダにはすでに何枚もの嵐山くんの笑顔が収められていた。テレビで見るようなキリッとシャキッとした笑顔や爽やかな笑顔、今みたいにおかしそうに楽しそうに笑ったり、はにかむし、さっきの仕方ないなあみたいに笑うのもある。それらぜんぶがすきだった。本人に伝えてもいいのだけど、いかんせんタイミングがまだないので言ってはなかった。今も、わたしの最優先事項はオムライスを胃に収めることである。腕時計で時刻を確認したのち、パクリと頬張った。
一緒に席を立ったのは一時十分前だった。食堂から三限の教室までは十分間に合う時間だ。嵐山くんの方はこれからパソコン室に向かうらしい。バッグを肩にかけ隣を歩く嵐山くんをちらりと横目で見上げる。秋服のカーディガンを羽織る嵐山くんは深緑という色合いもあってかテレビで見るより落ち着いて見えた。彼には色んな顔がある。いつも笑ってるわけじゃない。そういうのは実際に会って話してみて知った。
「間に合う?」
「余裕だな」
「防衛任務、二時からだっけ」
ああ、と短く答えた嵐山くんは見ていた腕時計をカーディガンの袖口に隠した。本当は四、五限があるらしいのに、ボーダーの防衛任務のため出席せずに基地に行くのだという。少し時間があるからパソコン室で講義のレジュメをコピーしてから行くのだ。概ね予定通りに動けているようでひとまず安心する。
第一校舎の前で別れる。次いつ会うかとかを約束する仲じゃないので、じゃあねと手を振るだけだ。「お仕事がんばって」「ああ、ありがとう」使命感や責任感がうかがえる、堂々とした表情。本当に立派な人だなあ、君といると、触発されずにはいられないよ。
「わたしも何か、役に立ちたいと思えるな、嵐山くん見てると」
「そうか?」
自覚がないのだろう、わずかに首を傾げてみせた嵐山くんに苦笑いしてしまう。そうだよー、と間延びした声で続ける。
「戦うのは絶対無理だけど、オペレーターとかどうだろう」
完全に思いつきだった。もっと程度が低ければ冗談とも言えてしまいそうな発言だった。きっと頼まれても実際にやりはしないと思う。オペレーターというか、ボーダーでの仕事が生半可な気持ちで務まるとは微塵も思ってない。それも、嵐山くんを見てればすぐにわかった。
「…大学生からだと少し難しいかもな」
じっとわたしを見る目と合う。なんか、嘘っぽい。だとしたら嵐山くんは嘘をつくのが壊滅的に下手くそだ。わかりやすいよ、びっくりするくらい。わざわざ追及したいと思うほどじゃないから、これも本人に言ったことはなかった。
|