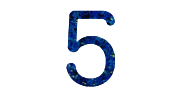
「ひっ……?!」振り返ったが尻餅をつく。大型近界民が迫っていた。迷う余裕はなかった。ここからまで十メートル程度。目測で確認しテレポーターを使う。瞬時にそばまで移動し、を抱える。緩慢な動きの近界民を避け、距離を取り屋根に登る。
「え、え?!」
目を白黒させているを一旦降ろす。テレポーターは簡単に言えば瞬間移動だ、目の前でそれをやられては驚くのも無理はないだろう。屋根に登らされたのも原因かもしれない。大型近界民にはすかさず充が突撃銃で応戦したため標的の沈黙には成功した。他の近界民の反応はない。近界民が警戒区域を越えることはなく、危機は回避することができた。……しかし。
「……」
肩で息をし辺りを見回しているに、何と声をかけたらいいのかわからなかった。
記憶封印措置について、俺はひどい制度だと思いながらも必要なものだと割り切っていた。トリガー技術は最高機密だ。これが外に流出することはあってはならない。近界民を倒す使命を遂行する、ボーダーが独占していなくてはならない。その道理は理解していた。もし流出しようものなら、そこから派生する問題は容易に想像できる。特に、広報活動をする俺たちは、メディアに流していい情報とそうでないものの境界は厳重に線引きされているのを知っていた。
記憶の処理はボーダー隊員に保護された市民に対し、機密保持のため適用される措置だ。制度の大きな目的としてそれがあるのは確かだが、おそらくボーダーへの不信が募らないようとの意味も含まれているのだろう。人の記憶にまで干渉していいのかと思わないこともなかったが、知らない方が幸せだという言葉があることから一概に悪いとは思えなかったのも本当だった。事実、警戒区域内で保護された小さな子供が、遭遇した近界民の記憶を封印されたことにより恐怖心を植え付けられずに済んだ例もある。
だから、今回も仕方ない。頭では理解しているのに、いや理解しているからこそ、彼女を見下ろす視線が定まらない。
の記憶が消される。
「………どうしてここに…」
声が震えていた。数十分後彼女に訪れる未来を予想し頭を壁に打ち付けられる感覚に襲われる。パッと見上げたと目が合う。トリオン体は夜でも目が利く。慌てて俯いた、バツの悪そうな彼女もよく見えた。さっき会ったときより小さい。そう思ったのもつかの間、は肩にかけたカバンの中をまさぐり、長方形のカードを取り出した。差し出されたそれに目を落とす。
「あの、カフェで嵐山くん学生証床に落としてたの!すぐ届けなきゃって思って、」
「! ……」
頭の中でガンガンと警鐘がなる。取り返しのつかない事態にはすでに陥っていたのにも関わらずそれは止まる様子もない。遅い、今さら何を、うるさい。何に八つ当たりしてるのか、俺は普段滅多に考えないような文句を何者かにぶつけていた。学生証は間違いなく自分のものだった。心当たりはすぐに思い当たる。携帯を探したときだ、全部物を出したあとしまい忘れていたのだ。「…ありがとう…」いっそ夢であってほしかった。おそるおそる手を伸ばす。血の気が引いたように、顔は真っ青になっていただろう。
彼女が警戒区域に入ったのは自分のせいだ。彼女はどこから記憶を消される?ここに入ったことだけでは足りない、俺の学生証を拾ってしまっている。持たせたまま帰したら何の解決にもならない。拾ったところが俺といた場所なら綺麗に消すには俺と会っていないことになる、ということは放課後から消されるのか、いや、それとも、まさか、
俺と初めて会ったところから。
「ごめん、連絡先知らなかったし、事務室とかに預けるってことも考えたんだけど、…だけど…せっかく仲良くなった嵐山くんと少しでも関わりたかったんだと思う」
優しいはずのその言葉はもはや太い針となって心臓を突き刺していた。息を上手くしている自信がなかった。
このときすでにわかっていたのだ。にとって今日初めて会った俺の印象がたとえいいものだとしても、危険を冒してまで俺と接触したいと思ったその気持ちも、綺麗に消されることを。申し訳なさそうに笑う彼女の、俺への感情は残らないことを。
「…あらしやまくん?」
「……」
さっきから顔が強張っている自覚があった。気付いたのかが心配そうに俺の顔を覗き込む。それにおそるおそる目を合わせる。彼女が瞬きをする。
「市民の方、一緒に来てもらえますか」
充の声がトンと落ちる。ハッと顔を上げると、屋根に木虎と二人で登ってきていたらしかった。市民の保護、ひいては記憶封印措置を施すためだ。冷静な二人は表情を崩さず近付いてくる。俺との時間が終わりを告げる。彼らに振り返ったは、この場に流れる重苦しい雰囲気を感じ取ったのか身を硬くした。もう一度、俺を見上げる。
「あ、あらしやまくん…」
「、…悪い、手間かける…」
肩に手を置き、充の方へ促す。は不安げに眉尻を下げたが、「ううん、全然」気遣うように首を振った。俺に心配かけまいとしたのだろうことが伝わる。それが余計、罪悪感を煽った。
「……巻き込んですまない」
「や、わたしこそ、ごめんなさい、お仕事の邪魔して」
「……」
「じゃあ、またあとで、ね」
「ああ…」肩から手を離す。硬い動きで手を振る彼女に、俺もなんとか振り返した。ぎこちない笑顔はお互い様だったろう。どっちもうまく貼り付けさえしていない笑みを見せ、ちょっと前の二人が見たら指差して笑ってしまいそうな、そんなチープで下手くそな、誰にでもできる、誰もしようとしないような嘘の笑顔で、見送って見送られようとしたのだろう。俺もわかっている。の笑顔が無理やり作ったもので、漠然と嫌な予感を感じているのだということを。彼女のそんな笑顔を見るのはこのときが初めてだった。はよく笑う女の子だった。それが身にしみて、俺もひどい顔をしていたと思う。
「…嵐山くんは笑って、ね」
右の腕をトンと叩かれる。が離れていく。今日会っただけの友人。充に支えられ地上に降りていくのを目にしながら、俺は手の中の学生証を強く握り締めていた。
その後、適用された封印措置によって、俺とは赤の他人となったらしかった。
◎◎◎
彼女が目の前でいなくなった感覚。俺は、大切な何かを失ってしまった気がしていた。
物思いにふけりながら久しぶりのキャンパスの地を踏む。九月の中頃、夏休みを終えた学生は約一ヶ月半ぶりの受講日を迎えていた。俺も例に漏れず、初日の講義に出るべく二限の教室へ向かっているところだった。火曜は二限から四限まで埋めているが、今日は午後から広報の仕事でテレビ局へ行く予定があるため一コマしか出られない。初日からこれかと苦笑せずにはいられないが、自分で決めたことだから文句は言えないだろう。
強い風が吹く。木々を揺らし緑の葉がいくつか流されていく。季節はもう秋だ。じきに紅葉し、コンクリート舗装された道は落ち葉で埋め尽くされるのだろう。
そんな移り変わりの情景を想像するけれど、図ったように眼前はちかっと光る。まだ未練がましく思い出す、彼女の後ろ姿だった。あまりの鮮やかさに思わず目を細めてしまう。
尊ぶべきものだったはずだ。手放したくなかった。それと同時に、手放さなくてはいけなかったと思っている。あの判断に後悔はない。しかし忘れることはできず、あれからずっと考えていた。
突然、後ろから追い抜かされた。走るその人が真横を通り抜け、ふっと風が吹いた。反射的に見えた横顔、なびく髪。肩にかけたカバンをまさぐる腕、取り出された携帯。……ピンク色のパスケース。
脳がはっきりと覚醒したようだった。すっと息を吸いながら、目は見開いていた。携帯を取り出した拍子に落ちた。あのときと同じだった。気付いたら駆け出していた。
ずっと考えていた。だから、確かめたい。確かめずにはいられない。それを拾い上げ、携帯を操作している後ろ姿へ駆け寄る。「あの」
「落としましたよ」
君から何をもらったのか、その正体が、知りたい。
「あっありがとうございます!……嵐山准?!」
「はい」今度こそなくさないよう。関係を再構築する。
|

