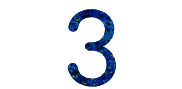

二限が終わるなり向かった食堂は当然のように混雑していた。昼休憩を大学で過ごすときは移動時間のタイムロスを考え毎回ここで時間を潰すことにしていたが、すぐに席を確保できたことは滅多になかった。一人なのでカウンター席か、せめて二人席に座りたいのだが、そういうときに限って四人席が堂々と空席だったりする。さすがにそこを陣取るのはひんしゅくを買うので目を離す。まいったな、と頭を掻いていた。こういう日に限って知り合いは見当たらない。そもそも水曜は約束をしなければ誰とも会うことがない日なのだ。仕方ない、おとなしく待つか。
「あ、嵐山、くん?」
ひかえめに肩を叩かれパッと振り返る。少し目線を下げた視界には女子学生がいた。緊張でこわばった笑顔でおずおずと会釈をした彼女には見覚えがあった。
「今朝の…」
「あ、はい!そうです」
今朝拾ったパスケースの持ち主だ。言い当てると彼女はホッとしたのか今度は緊張を解き、朗らかに笑った。
「嵐山くん、一人なんですか?」
「はい。だから席を探してるんですけど、見つからなくて」
「じゃあ、わたしと一緒に座ってくれませんか?!」
予想外の申し出に驚くと、彼女はハッとし慌てた様子で弁明のような説明を加えた。「あの、わたしも一人なんですけどたまたま空いた二人席を取っちゃって、気まずかったんです!」暗にやましい意味はないことを伝えたかったのか、そう手を振る彼女にもちろん悪意は感じられなかった。それにその気持ちはよくわかる。こちらとしてもありがたいし、断る理由は特になかった。
「ぜひ」
その返答に彼女はホッとしたような嬉しいような、そんな笑顔を見せた。
お互いすきなものを注文し、向かい合った二人席に着く。彼女の薄緑のトレーには丼に盛られた月見そばが乗っている。それを見ながら、醤油ラーメンを乗せたトレーにバッグから取り出した緑茶のペットボトルを置く。朝学校に来る前にコンビニで買ったものだ。彼女の方はステンレス製のマグボトルをカバンから取り出していた。では、とどちらともなく姿勢を正す。
「いただきます」
両手を合わせてあいさつを唱え、食事を始めた。という名前の彼女とは歳が同じということを確認してからお互い敬語をやめにした。そうするとさっきまでのよそよそしさはすぐに消え、彼女とはあっさりと打ち解けることができたのだった。
俺のことはボーダー隊員としてテレビでよく見ていたから知っていたと言い、本当に通ってたんだと感慨深げにじっと見られた。よくあることだったが、こうしてテーブルを挟んだ距離でまじまじと見つめられるのは経験になかったのでさすがに少し落ち着かない。苦笑いをすると慌てて謝罪されたので、気分を害したわけじゃないと弁明した。それには彼女も苦笑いで、肩をすくめる。
「あはは……ほんとごめん」
「いいよ。はボーダーに興味があるのか?」
「んー…?」
「ん?」
テレビでよく見てたと言ってたからてっきりボーダーに関心があるのかとばかり思っていたが、そういうわけでもないのだろうか。最近はボーダーの存在が当たり前になりつつあり、警戒区域内のみでの活動をしているせいか市民の中には近界民やボーダーにあまり関心を持たない人も増えてきている。無関心はいざというとき危険を招く。そんな市民を減らすことが、俺らのように隊員が広報活動をする目的の一つだ。
「あんまり活動内容は知らないんだよね」
「そうか」
「でも近界民をやっつけてくれてるってのはわかってる!わたしには絶対無理だ」
「戦闘員がすべてじゃないさ。オペレーターやエンジニアとして市民のために戦っている人たちは大勢いるよ」
「あ、オペレーターはわりと学生も多いんだよね」
「ああ、というか、ほとんどそうだな」
「へえー…」
素直に感心したように相槌を打つ。広報活動の目的には新規入隊者の勧誘も含まれている。ボーダーは常に人手不足だ。戦闘員もオペレーターもエンジニアも余裕がない。見る限りは勇敢なところがありそうだし、市民を守りたいという気持ちがあるのなら、ぜひ入隊も考えてもらいたかった。
「みんな偉いなあ…」
「……」
「あ、でも偉い代表は嵐山くんだよね」
「俺?」
首を傾げるとは「え」と表情を固めた。
「当たり前だよー?!テレビで見る嵐山くん本当に同い年かってくらいしっかりしててほんと偉いなってずうっと思ってたんですよ?!」
「そ、そうなのか」
突然力説されてどもってしまう。頬を紅潮させ箸を持った手でテーブルをぺしんと叩く彼女の剣幕に思わず身を引いたが、妙な説得力があってなるほどと納得できてしまった。嵐山准だと声を上げた今朝の様子から、彼女が俺に対してそう思っていることは本当なのだろう。それは素直に、光栄だった。
賞賛の言葉はこれまでにもさまざまな人から伝えられてきた。全員が全員同じ気持ちでその言葉を伝えてきたとは思っていないが、ほとんどは俺やボーダー隊員への感謝だったり尊敬だったり、いい意味合いで送られるものとして受け取っていた。それを俺はしっかりと糧にして、ボーダーとして責任や誇りを持って活動を続けている。
そう、だから彼女の言葉も、俺はもれなく受け取って、糧にする。屈託のない真摯である言葉に目を伏せる。
「…ありがとう」
感謝の言葉にはわずかに身じろぎしたらしかった。「…ううん」そう返す彼女の声さえ心地よい気がして、ゆっくりと瞬きをする。顔を上げると彼女は見るからに照れていたようで、俺もなんだか照れくさくなって笑ってしまった。
ボーダーの話は一旦終わりにして、世間話に移行した俺たちは三限が始まる十分前まで昼食を食べつつ話を続けていた。
は俺と同じで水曜は友人と会わないらしく、このあと一人で受ける授業を寝ないようにするのが大変なんだという。
「そろそろ行くよ」「ああ、講義頑張れ」席を立つ彼女へ激励を送ると、相手はかみしめるような笑顔を見せ、うんと手を振った。初対面とは思えないほど気楽に話せた彼女にある種の感慨を覚えつつ、俺は授業へ向かう彼女を見送った。
|