
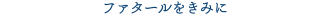
一日すべての講義に出席できるのは今週に入ってこの水曜が初めてだった。明日あさっては日中の防衛任務が入っているから出られるのは二限までだ。出席点を取る講義は選んでいないが、単位修得方法はレポートと試験の数が半々だ。講義内容が重要であることには変わりない。しかし中には生で受けた回数が半分程度の講義もあり、休んだ日は友人に頼りきりなのが現状だった。これで試験を乗り越えられるのか、と再来週に控える試験期間に一抹の不安が頭をよぎるが、市立大学のためボーダー隊員の学生への考慮は十分にされていることを考えると甘えたことは言ってられなかった。
二日ぶりの大学に足を踏み入れる。構内の植物は発色のいい緑に色づき、夏の盛りを表していた。歩く学生もほぼ全員が半袖の涼しげな格好をしている。ほとんどが一限の授業を受けるべく校舎へと向かっているようで、手前で曲がる食堂への道を行く人の姿はほとんどない。かくいう俺も、目的地の図書館が校舎の隣のため、その流れに混ざって歩いているのだが。
本来水曜は二限からだったが、今日は大学の図書館で自習をしようと早く来たのだ。試験範囲がすでに発表されている科目の教科書をバッグに入れてきた。空き時間に比較的利用している図書館の自習スペースはよく集中できるのだ。周りの話し声が聞こえる食堂もそこそこ好んではいるが、今回は二限の教室への移動効率も考えて図書館に決めていた。二限を受けたあとは三限が空くから、そのときは食堂でいいかと思う。
普段通りのスピードで歩くと男女二人組の横を追い越した。彼らが後ろで「嵐山准だ」と言ったのを聞き流す。七月にもなった今では大学での奇異な視線はもう慣れていた。もともと自分はそういうのにあまり頓着するたちじゃないらしく、入学当初から妙に目立ったところで特別得意にもならなかったし苦だとも思わなかった気がする。自分が有名人と認知されている自覚は、あるつもりなのだが。
ああでも、声をかけられて足止めをくらうときはさすがにびっくりするな。
なんとなく思ったのと視界で違和感が生じたのは同時だった。
前を歩く学生がカバンから何かを落としたのだ。迷わず駆け出し、薄い長方形の落し物を拾う。パスケースだ。足を止めずそのまま後ろ姿へ近寄る。持ち主である彼女はこれを落としたことに気付いていないようだった。
「あの」
声をかけつつ肩を一度だけ叩く。突然の刺激に反射的に振り返ったその人は俺と目が合うと両目を一層丸く見開いた。その視線の類になんとなく察しがついたものの先述した通り特に気にならず、俺は当初の目的通り今しがた拾ったそれを差し出した。
「落としましたよ」
「……嵐山准だ!」
それには「はい」と笑って返す。素直に驚きの感情をあらわにする彼女は口をぱくぱくと動かしたあと、それからハッとして俺の手が持つパスケースを、仰々しくも両手で受け取った。
「あ、ありがとうございます…!」
「いえ。そのパスケース、可愛いですよね」
「え…?!」
「妹が同じの持ってるんです」
拾った瞬間気が付いた。買い換えたといって最近佐補が真新しいパスケースを母に見せていたのを思い出した。それと同じだったのだ。薄いピンク色の生地にキャラクターがチラシ柄にプリントされているもので、色違いがあってもよさそうだが今目の前の彼女の手にあるのは色もデザインも佐補のとまったく同じものだった。
「へー妹さんがいるんですか…」
「はい。妹と弟が。中学二年生の双子なんです」
「え!珍しいですね!」目を輝かせた彼女の言う通り男女の双子というのは珍しいらしい。妹たちに興味を示してもらえるのが個人的に嬉しかったのもあり、二人とも可愛いきょうだいですと答えると、彼女は少しポカンと呆けたあと、へにゃりと眉尻を下げて笑った。
「伝わりました」
「……そうですか…」今さら気恥ずかしくなった俺は頬を掻いてごまかした。初対面でそう話すこともなく、沈黙ができるかと思う前に、「あの、じゃあ……ありがとうございました」相手の人が深々と頭を下げた。
「いや、大したことはしてませんよ」
「……」
顔を上げた彼女はやはり目を潤ませたように光らせて、口はぎゅっと閉じ何かをこらえているようだった。けれど実際声にすることはなく、嬉しそうな笑顔を見せて踵を返したのだった。
俺はなんとなくその場から動き出せず、しばらくして、校舎へ駆ける男子学生に追い越されてやっと、図書館へ歩き出すことができたのだった。
|