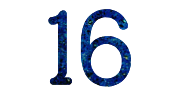
今日の防衛任務は夜の八時からだった。午後にレポートを仕上げるため大学のパソコン室に来ていたとたまたま会い、お互い無事提出し終えたあと、さっきまで喫茶店でのんびり話をしていた。放課後の時間を共に過ごすことは滅多になかったものの、数少ないうちで喫茶店に寄るときはだいたい三ヵ所の店を空席状況を見て選ぶ流れができていた。今日は俺の移動時間も考慮したうえで大学から一番近い店にしてもらった。
そこはと初めて会った日に行った店だった。以前にも彼女からの提案であの喫茶店に行くことはあったが、そこでのやりとりで何かを思い出す気配はなかった。こじ開けられない彼女の記憶の封印は俺とのファーストコンタクトを見事に封じ込め続けていた。彼女自身は至って平穏に生活している。ときおり虚しい気持ちに襲われることはあれど、概ね俺自身も見守りながら安心していた。
作戦室のソファに座って読んでいた資料が、焦点がずれたせいで次第にぼやけていく。そのまま思考は別のことで回転し始める。…あの日のエンジニアや上層部の判断に異論はなかった。それが今になって、誤っていたかもしれないと思うようになっていた。
封じられた記憶には近界民との遭遇、それに伴う恐怖心も含まれている。通常ならそれを忘れさせることは、トラウマになる危険性を考慮し必要なことだった。しかし彼女は近界民への危機感が人より薄い人間だ。話を聞く限りでは四年半前の第一次大規模侵攻の際、遠くにいて実害を受けなかったことが原因のようだった。彼女のような人が他にも大勢いることは容易に推測される。しかし彼女の場合、現在ボーダー基地が見えるほどの距離にある大学に通う身だ。近界民への危機感は養ってもらわないと困る。そのためには、あのときの記憶を持っていてほしかった、と思うのだ。
……いや、そういってもっともな理由をつけたいだけで、本当は単にが自分との記憶を忘れてほしくなかっただけかもしれない。俺は物分かりのいい人間を装った偽善者なのだ。だから今更なことを言って責任転嫁しようとしているに過ぎない。自分で自分が情けなかった。
先週、彼女に思わず強く当たってしまったことを後悔していた。あれから怪しまれるようなことはなく安堵したが、明らかに不自然すぎた。俺はあのとき間違いなく、が危ない目に遭うことだけじゃなく、また記憶を処理されてしまうことを恐れたのだ。もう俺との何ものも、忘れてほしくなかった。
向かいに座っていた充が立ち上がったのにつられて顔を上げる。視界に入った時計は八時十分前を示していた。資料が挟んであるバインダーをテーブルに置く。
「そろそろ行くか」
「はい」
防衛任務までの少しの時間手をつけていた資料を手早くまとめテーブルに重ねて置く。すべて三月の入隊日に関するものだった。この間の記者会見以降ボーダー入隊希望者が続々と集まっており、四ヶ月に一度の一斉入隊じゃ捌き切れないということになったため、急遽月一でのそれを実施することになったのだ。
まだ急ぎのものはないためそこまで多忙ではないが、そのうち空いた時間はこの事務仕事に充てないとならなくなるだろう。今日みたいな日は大学の用が終わったらすぐに基地に行かないとな。…と春休み会えるだろうか。時間があれば誘おうとは思っているが、さすがに私事と市民の安全を天秤にかけたら優先順位ははっきりしている。任された役目に文句を言うつもりはなかった。
そういえば、今日は夏のあの日と同じだな。
唐突に思い出した。水曜という曜日も、さっきまでと喫茶店にいたことも、防衛任務の開始時刻も同じだった。シフトの組まれ方は色々パターンがあるとはいえ同じ時間に入ることは多々ある。だからそんな珍しいことではないのだが、なぜかこのとき、自分の心臓あたりがざわついていることに気が付いた。
ふと、なぜか気になって、荷物がしまってあるロッカーを見遣る。
「嵐山先輩?」
「…ああ、すまん」
入り口に立つ木虎に振り返り、俺は足を踏み出した。
◎◎◎
「あれ」
トイレから自分の席に戻ってきたところで見慣れないものが目に入った。それはテーブルの片隅にポツンと置かれており、わたしの荷物が広げてあるところから対角線で結んだところにあった。入店したときはなかったはずだから嵐山くんの忘れ物だろう。瞬時にその思考に至り、控えめに置かれた長方形の小さな薄い板を手に取った。
「学生証…」
裏返しになっていた大学の学生証だ。そういえばさっき嵐山くん、バッグひっくり返されてたよなあ。隣の席に座ってたお兄さんのイヤホンコードにひっかかって床に全部ばら撒いてた。わたしも拾うの手伝ったけど、学生証は触った記憶がない。
それを持ったまま、座りながら少し推理してみる。嵐山くんとわたしとお兄さんがすぐにかき集めてバッグに戻したけれど、きっと学生証だけ拾い忘れてたんだ。それで、わたしがトイレに行ってる間に床に落ちてたそれに気付いた誰かが、持ち主が座ってるであろうこのテーブルに置いて去って行った。クールな人だったのか、伏せた状態で落ちてた学生証の顔写真の方は見ずにサッと置いたのだろう。あの嵐山准の私物だと知ってたらこうはいかないはず。少なくともわたしやわたしの友達だったら、ここに嵐山准がいると知った途端一人でそわそわして待って、戻ってくるであろう嵐山准に手渡しで返してたと思う。残念ながら、嵐山くんはもう防衛任務に行ってしまってここには戻ってこないのだけど。もしかしたら拾い主は、この席に残ってるカバンや筆箱を見てここにいるのは女一人だけだと察したから、テーブルに置くだけにして颯爽と去ったのかもしれない。
両手で学生証を顔の前まで持ち上げ、左の正方形に区切られた枠の中に映る嵐山くんと向き合う。三門市立大学はここに使う証明写真を受験の願書に貼られたもので代用するので、彼も首から下は高校の制服が見えていた。まっすぐ前を見る、今よりいくらかあどけない嵐山くん。そんな彼と目が合った気がして、わたしは途端、ひらめいたことに頭を支配された。
嵐山くんに届けてあげよう!
それはとっても名案だった。もう春休みに入っているので嵐山くんも大学には当分行かないと言っていた。わたしがこのまま持っていても次いつ会えるかわからない。それなら今日届けた方がいいはず。わたしもどうせそろそろ帰ろうと思ってたし、ボーダーの基地も目に見える距離でそんなに遠くない。
「……」
とかもっともな理由をつけて、単に嵐山くんに会いたいからなんだけど。一応大学の事務室に届けるという選択肢だってあるわけだ。
でもあえて一番手間になりそうなことをしようと思うのは、すぐに届けて少しでも嵐山くんの役に立ちたいという自分勝手な押し付けと、無理にでも会えるくらい嵐山くんと親しい間柄であるという優越感に浸りたいからなんだろう。どのみちロクな動機じゃないのは確かだ。
(わたし嵐山くんのことすきなんだなあ)
ぼんやりと思って、でも仕方ないという観念もしていた。あんな人が近くにいてすきにならないわけがない。当然だとすら思うよ。テレビで見てたときから、彼を人として尊敬してたくらいだ。わたしは嵐山くんのことを最初から、少なからず、いいやかなり、特別視していた。それが結果的に好意へと変化を遂げただけ。これだけ一緒にいたらそりゃー、すきになりますわ。おそるべし、心からの好青年。
だから多分、これが最近知り合ったくらいの関係でもこうしてたと思う。むしろ浅い関係だった頃の方が、周りの人とは違うんだっていう優越感と彼への好意に素直に動いてたんじゃないかな。そうやって自己分析に励みながら、わたしは荷物を簡単にまとめ、三分の一ほど残っていた抹茶ラテを飲み干した。返却口にグラスを返し、一目散に喫茶店を飛び出す。
基地は当然ながら警戒区域に囲まれたところにあるので、そこへ行くには立ち入り禁止の放棄地帯を通らなければならない。ボーダー基地に一番近いバス停で降車し、夜闇にそびえ立つ四角錐台の建物を仰ぐ。ずいぶん遠い。今まで知らなかったけど、放棄地帯というのは相当広いようだ。腕時計を確認する。時刻は八時十分前。まだ嵐山くんは任務じゃないだろう。
再度明かりのついてない住居やマンションを見遣る。綺麗に残っているにも関わらず、人の気配は一切ない。棄てられたんだから当たり前だ。そんな冷淡な答えが出て我ながら少し驚く。動揺を溜め息でごまかして、スンと鼻で空気を吸い込んだ。
それからぶるっと身震いする。二月の半ばは相当冷え込む。でも震えた理由はそれだけじゃない。ここからのことを深く考えてなかったわたしは、この有刺鉄線の向こう側がまったくの別世界に思えて少し恐怖を感じたのだ。まぶたの裏でチカチカと何かが爆ぜる感覚が、さっきからしていた。
唐突にハッとして、携帯を取り出す。そういえば肝心の嵐山くんに連絡してなかった。せっかく連絡先知ってるんだから、使わない手はない。学生証が落ちてたよって、今から届けに行くよって言わないと。電話を掛けてみるけれど出ず、仕方なしに次の手段としてメッセージを送ることにした。
(い、ま、か、ら、……)
文章は決まっていた。けれど自然と、ピタリと、画面のキーパッドをフリックする親指が止まった。思い出すのは先週の彼だった。
初めて聞いたわたしへの懇願。危険から逃げようとしなかったことに、嵐山くんは酷く憤りを見せていた。まるで悲しそうでもあった。あれをさせたのが自分だと思うと後悔や自責の念に駆られてやり直したい気持ちになる。先々週の大規模侵攻から翌週嵐山くんと会うところまでを、一回全部なかったことに、すっかり忘れてしまいたかった。もちろん、そんな都合のいいことは起こりえないけれど。
すうっと大きく深呼吸する。あれがあったのに今この境界線を飛び越えることは、嵐山くんの意に反するんじゃないか。ここまで来てやっとそんなことに気付く自分の馬鹿さ加減が恥ずかしかった。思わずしゃがみこんでしまう。
(えっと、じゃあ…)
嵐山くんを悲しませないように、嫌われたくないわたしがここからとるべき行動。
メッセージを途中まで消し、打ち直す。送信完了の文字が下部に表示され、わたしは携帯を胸元で抱きしめながら、曲げた膝に顔をうずめるのだった。
寒空の下、どこか遠くでは建物が崩れるような瓦礫の音が聞こえていた。
|

