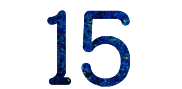
大学の出入り許可が降りると同時に講義が再開されたのはそれから二日後のことだった。よりによって重い時間割の水曜か、と頭を抱えたものの早く学校に行きたいと思っていたのもあるため複雑な心境である。一限に合わせた時間より三十分も早く家を出、わたしは月曜の昼にいた大教室へ足を向けた。もちろん嵐山くんのシャーペンを探すためだ。心臓が嫌な動悸を打ちながらも教室のドアを開けると、案の定学生の姿は一人も見えなかった。逸る気持ちであのとき座っていた席のそばまで来る。机の上には何もない。しゃがんでワックスがうっすら見える床へ目を滑らせるけれど、ご丁寧に閉鎖中清掃がかけられたようでゴミ一つ見当たらなかった。
「…あー……」
いよいよがっくりと頭を垂れる。胃がキリキリと悲鳴をあげていた。
その日は水曜だったけれど、嵐山くんとは会うことはなかった。ボーダーの方がまだ慌ただしいから大学に行けないとの連絡を事前にもらっていたのだ。そもそも約束するような間柄ではないのだけれど、いつの間にか水曜の昼は二人で食べるのがお決まりとなっており、わたしも水曜に食堂に来る際はカウンター席じゃなくて二人席を探すようにしているし、向こうもそうらしかった。そのため嵐山くんは気を遣って、来れない日はあらかじめ断りのメッセージをくれるのだった。律儀だなあ、と受信するときはいつも思っているのだが、この日ばかりは安堵の気持ちの方が勝った。
◎◎◎
それから次に嵐山くんに会ったのはちょうど一週間後だった。ようやくボーダーの仕事がひと段落したのか、久しぶりに会った嵐山くんはどこか疲労感を滲ませて苦笑いした。
「お疲れさまでした。あと、ボーダーの皆さんには大変お世話になりました」
「なんだ、他人行儀だな」
二人のトレーには同じ定食が乗っている。向かい合って座り、仰々しくお辞儀をする。感謝を伝えられるのが嵐山くんしかいないのだからこうなるのは仕方ないだろう。そりゃあ迅くんや太刀川さんとも一応顔見知りにはなったけど、外で見かけたところで駆け寄って今のと同じことを言えるかと聞かれたら首を振る。わたしのコミュニケーション能力を買い被らないでほしい。
他人行儀になってしまうのは感謝の気持ちを誠心誠意伝えたかったからです。……いいやすみません。本当は、嵐山くんに対して後ろめたかったのだ。いつ切り出そうか迷っている間に食事は進み、あっという間にハンバーグ定食のハンバーグはあと一欠片となってしまう。嵐山くんの方はもう食べ終わって、ペットボトルのお茶を飲んでいる。三限までのタイムリミットももう余裕はない。今日を逃したらますます言いづらくなることは十九年生きてきた経験から明らかだった。わたしは意を決して、暴露することを決めた。お箸を持ちながら背筋を伸ばす。
「嵐山くん、あの、謝りたいことがあるんですけど」
「謝りたいこと?どうした?」
「ええ、実は嵐山くんからもらったシャーペンなんですけど…こないだの避難のときに、なくしてしまったんです」
嵐山くんが呆気にとられた顔をしたのはわかった。わたしはバツが悪すぎて、つい逃げるように俯いてしまう。「…そうか」ポツンと落ちた声にビクッと大げさに肩を跳ねてしまう。思ったほど怒気は含まれてない、というのはあとになって思い返して感じたことだった。このときは申し訳なさに内心慌てふためいていたので、嵐山くんが何か続けようとしたのさえ遮ってしまう始末だった。
「でも、」
「ごめんなさい!教室で筆箱広げたままご飯食べてて、急いでしまったつもりが忘れてたらしくて、」
「あ、ああ」
「確認しようと思って途中で一回引き返そうと思ったんだけど、」
「…なに?」
ピクリとわかりやすく嵐山くんの眉が動いた。その声の低さに驚いたわたしは口には出さず、え、と顔を上げた。空耳かと思ったのだ。しかし嵐山くんの険しい表情を目にし、勘違いじゃないと確信させられた。あらしやまくん、と名前を口にすることすらできなかった。彼がこんなに怒りをあらわにしてるのは初めて見たのだ。
「シャーペン一つのために…そんな危険なことは絶対にするんじゃない!」
声量こそそこまでじゃなかったものの重厚感のある声音にわたしは呆気なくひるんだ。怒ってる?というより、なんだこれは。でも責められている、のか。嵐山くんがわたしを叱責している。
あの嵐山くん、誠実で気さくで明るくて親切な嵐山くんに、怒られた。わたしは、ここ最近この件に関して酷使していると思ってた胃や心臓が、まだまだだったと気付いた。今の痛みや動悸には到底敵わない。指先がサッと冷たくなっていた。
「あ、あの…」
「……すまない。違うんだ。あれならまたあげるよ。だから…」
ハッとしたと思ったら今度は顔を青くした彼は額に手をやり、かぶりを振ってそう続けた。そんな様子を気にかける余裕もないわたしは彼から逃げるように俯く。
「ご、ごめんなさい…」
羞恥で顔から火が出そう。このとき、わたしはこれを言えば嵐山くんは悪い気はしないんじゃないかと思ったのだ。みっともない自意識をあばかれた気になる。恥ずかしい。しにたい。
「違う、言いすぎた、悪い。でもそんな、自ら危険に飛び込むようなことは絶対にしないでくれ。頼む」
嵐山くんらしくない釈明と悲愴に満ちた懇願にはゆるゆると頷く。嵐山くんがあからさまにしまったという顔をしていたことには、俯いたままのわたしは少しも気が付かなかった。
|

