
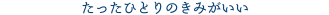
「嵐山くん決めた?」
「やっぱり山菜そばだな」
「あ〜いいね〜〜」
「は?」
「うあ〜〜……山菜そば!」
顔を両手で覆い隠し決断したに思わず笑いが漏れた。「ラーメンじゃなくていいのか?」食堂のメニューを見るまでは今日はラーメンの口だと豪語していた彼女だったが、サンプルケースの前に立って悩んだ数十秒のうちに気分が変わったらしかった。
「嵐山くんが選んだものがよく見える病気にかかっている」
「はは、またその病気か」
悔しそうにサンプルケースの上段に鎮座する偽物の山菜そばを睨めつける。前にも言われたことがあるその症状は、まあ、気持ちがわからないことでもない。人が食べてるものが美味しく見えるというあれだろう。決まったことだしとどちらからともなく動き始め、そばとうどんの受け取り列に並ぶ。近くのトレーが積み重ねられた台車から二枚取り、一枚をに渡す。混雑時だがラーメンほどの人気はないためわりかし早く俺たちの番になり、各々同じものを注文して受け取った。会計も済ませ、箸を取ってあらかじめ確保しておいた二人席まで行く。今日は来てすぐ見つけられたので時間にはいつもより余裕があった。とはいえ、早く出なくてはいけないのだが。
「いただきます」
水筒とペットボトルを出し準備が整ったところであいさつを唱える。箸を取って伸ばした先の丼からは湯気が立ち昇っていた。一応温冷どちらも選べたが、二人が選んだのは温かいそばだった。十二月にも入って季節は冬だ。温かいものを食べたいと思うのは当然の欲求だろう。
上層部に呼び出しを受けた日からすでに二十日ほど経っていた。呼び出されたのは結局あの一度きりで、迅の予知で懸念が解消されたからなのか、俺との関係を断絶するよう執拗に迫られることはなかった(根付さんからは別の意味で立場を考えて行動しろと言われるようになったが)。しみじみと、迅のサイドエフェクトとそこまで信用されるに至った彼自身に感謝の気持ちを持たざるをえない。あれからしばらく会えていないが、今度会ったらちゃんと礼をしようと思う。
「そういえばネットでちらっと見たんだけど、警戒区域外で近界民が出たってほんと?」
ピタリと箸が止まる。そう、個人的な問題が解消したと思った矢先の現在、市内では深刻な問題が発生していた。
「ああ」
「まじか。やばいね」
「…市民には流せない情報なんだ。悪い」
箸を持った右手の人差し指を口の前で立てる。秘密というジェスチャーだ。それを見たは目をまん丸にした、と思ったら、変な風に笑顔を作った。「だいじょうぶっす…」ほうけたような返事に心配になったが、黙秘権を使ったことに気を悪くしたわけではなさそうだったのでとりあえず安心する。
昨日の夕方から今まで警戒区域外で六件のイレギュラーゲートが確認されていた。場所や時間に規則性はなく、原因も不明。いずれも近くに非番のボーダー隊員がいたため被害者は出ていないのがせめてもの救いだった。ゲートの多くはボーダー基地の周囲で開いているため、誘導装置が機能していないわけではないのは確かだ。しかしそれの効かないゲートが発生している。現在エンジニアが究明に当たっているが、現時点でも謎のままだった。
「とにかく、警報には気を配ってくれ。シェルターの場所は把握してるか?大学と家だけじゃなく通学路で遭遇したときの避難経路も…」
「う、うん……前も思ったけど、嵐山くんってお母さんより心配してくれるよね」
まじまじと見上げられ、思わず、う゛、と返答に詰まる。つい目を逸らしてしまう。そこまで口を酸っぱくして言ったつもりはないが、にはそう取られたらしい。確かにこの手の忠告は今までに何度もしていた。
しかし夏のあの日のことを思うと言わずにはいられない。はあの日、二体の近界民に追われ恐怖を味わったことだろう。武器を持った隊員ですら最初は恐怖心を覚えるというのに、何も持たない生身の人間があの異世界の兵器を目の当たりにして怖くないはずがない。もう二度とあんな目には遭わせたくなかった。たとえ、彼女がもう覚えていなくとも。
…それにしても、母親と同じという評価は、正直複雑だな…。よほど苦い顔をしていたらしく、は今度はふっと吹き出した。
「うそだよありがたい友達です」
「と、…ありがたいか」
友達という言葉に反応しそうになるのをこらえ、もう片方の表現に触れる。家に招いたときもそうだったが、にとって俺は堂々と友人のポジションであるらしかった。そりゃあまだ何も伝えていないから、当然といえば当然なのだが……いや、察してほしいというのは男らしくないな。
「ほらわたし、男友達ほんといないからさー」
「…そうなのか?」
「そうだよー大学で友達っていえるの嵐山くんくらいしかいない」
は斜め上を見上げ考えるそぶりを見せ、そう断言した。「学生じゃないけどあと迅くんもか」確かにこれまでの話の中で男の影を見せていなかったが、そこまではっきりしてるとは思わなかった。性格的に友達が多そうなイメージがあるが、異性の交友関係は狭いらしかった。
それにホッとすると同時に喜びさえこみ上げてくるものだから、大概単純な人間だろう。俺が今、に一番近い男だ。思うとにやけそうになる顔を抑えるのが大変だった。
それからちょくちょく会話を挟んで昼食を済ませた。腕時計で十二時四十分を確認し、ペットボトルの緑茶を一口飲む。
「じゃあそろそろ行くな」
キャップを締めバッグに放り込む。席を立ちながらそう言うとまだ食べている途中のは顔を上げ、同じように腕時計を見た。
「もうか」
「ああ、悪いな」
コートを羽織り、バッグを肩に掛ける。今日は一時から防衛任務があるのだ。急げば間に合う計算だ。少々慌ただしくなることは承知の上で、他のメンバーも昼食を済ませてから本部に向かう話になっている。普段はもう少し余裕のあるシフトを組まれるのだが、さっき話に上がったイレギュラーゲートの件もあり、防衛任務に多くの人員を割いているらしかった。
「ごめん、ありがとう」
「? 何がだ?」
「忙しいのに付き合ってくれて」
「俺が一緒に食べたかっただけだよ」
申し訳なさそうに言うが気を病まないよう笑って返す。それは本当で、時間の合間を縫ってでも会いたいと思っているのはもっぱら俺の方だった。むしろ一人にして悪い。謝る前に、へにゃりと笑って「ありがとう。お仕事頑張ってね」と送り出してもらったので、謝罪の言葉は飲み込んだ。軽く手を挙げ踵を返す。嬉しい激励に口が緩むのを手で覆い隠し、すれ違う人にばれないようにしたものの少し不自然だったかもしれない。
|