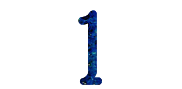

友達は食堂があんまりすきじゃないんだそうだ。理由としてはメニューが少ないとかおいしくなさそうとか料理を食す場所として根本的な点に不満があるのも確かだけれど、一番重篤な問題として、ピーク時とっても混雑してるというのがあった。特に大学一年生のわたしたちはまだ食堂を我がものにはできておらず、かつ一年生であるがゆえに履修科目が多く時間割はキツキツで、二限と三限の間の昼休憩に食堂に行ったところで席が取れた試しがなかった。ダメ元で食堂を覗いて、四人席は確保できず、時間を無駄にした感の拭えないまま大学外のファミレスに行く。七月の中旬に突入したこの頃では食堂を覗くことすらなくなっていた。
一人席ならまだ、待ってタイミングを図れば取れないこともないと思う。密かに思うわたしはいつか一人のとき行ってみようと計画を立ててはいるのだけれど、未だに勇気が出なくて実行に移せていなかった。だってすごい混んでるし、その中にぼっちで座ってご飯食べるって、そこそこ居心地悪そうだよ。想像だけで心が折れるわたしは一人、四人テーブルに目を落とす。今日は少し足を伸ばしたところのピザ屋さんに来ていた。お皿はもう片され、テーブルには四人分のお冷とセットドリンクのグラスが置いてある。オーダーからサーブが早いおかげで食べ終わったあともゆっくり話す時間があった。
「えーほんとに四塚市の大学なんだ」
「おしい!」
「おしいの?」
テンポのいいやりとりにあははと笑う。同じ学部のこの三人とは仲がいい。みんな自由人なので必修じゃない選択科目の授業は見事にバラけてるけど、それ以外だと大教室で待ち合わせて席を近くにしたり、授業終わりに遊んだりする。気の置けない間柄の友達がこんなにあっさりとできたのはこの大学に入って一番よかったことかもしれない。
「で、何の話?」
「聞いてなかったのかよ」
「なんで今笑ったの?」
「笑いどころだと思った」
すかさず返すと「でた!」とまた笑いが起こる。それにつられてわたしもケラケラ笑う。楽しいなあ。
「ほら前話したじゃん、わたしらと同い年のアイドル!」
「あーあの金パの!」
「そう!あの人やっぱ四塚市の大学にいるんだって!」
「へー、四塚市ってそこそこ近いよね」
同い年のアイドルが四塚市の大学に入学していたらしい。行ったことないけど、海に面してるのに緑も多くてのどかな町だったって誰かに聞いたことがある。でも大学があるのは初耳だったなあ。向かいの友人がうんうんと大きく頷く。
「近いよ!おしいでしょ?」
「確かにおしい」
「いえい」
ピースをしたその子に隣の子が変なものを見る目を向ける。タイプの違う自由人の集まりだけど、みんなミーハーであることには違いなかった。わたしもアイドルとか有名人とか生で見てみたい。
「でもウチにだって嵐山准がいるじゃん!」
そう言ったのはわたしの隣の子だった。三人の視線がビッとその子に集まる。
「それね!!嵐山准!!」
「三門市の有名じっイタッ?!」
途端にぎゃあっと盛り上がるテーブル席。向かいの子なんて興奮してテーブルを叩いたら角に指の関節をぶつけてた。それが面白くてまたドッと笑う。めっちゃ痛そうにしてるよ。その子は痛みに悶えながらも「生で嵐山准見たい」と懸命に主張している。もうなんでも面白い。ツボに入って目に涙を浮かべてしまう。
「あー面白い」
「実際嵐山准て大学いるの?誰も見たことないよね?」
「ネッシーかも」
「もうやめてえ」
ヒーヒー言ってるわたしの横では友達が冷静に何学部だとか何曜日の何限の何の授業に出てるだとかの情報をリークしてくれたけど、先ほども述べたようにわたしたちの時間割は無駄なくキツキツに詰めているので残念ながら彼の目撃情報に合わせることはできなかった。みんな大学にいる時間を最小限にし、かつ週休三日を取るべく、必修科目と必修科目の間に自由選択科目を敷き詰めた結果、空きコマという不存在から縁遠い学生となってしまったのだ。笑いの波がそろそろ落ち着いてきたわたしはゆったりとソファ席に座り直し、はーと息を整える。
「、嵐山准見たことないよね?」
「ないよー」
「せっかく有名人が同じ学校通ってるのに損してる気分だよね」
「確かに」
「でもさー有名人っていっても三門市内限定の有名人だよね」
斜め前の子が頬杖をつきながら言う。それも確かに。嵐山准は三門市の有名人だ。それは市民にとってなくてはならない存在の機関に、彼が所属しているからだ。ナントカ防衛機関、ボーダー。三門市にときおり出現する近界民という怪物と戦う勇敢な人たち。その中でも彼は特に、いわゆるボーダー代表だった。逆にいえば、ボーダーのありがたみをよく知らない市外の人たちからしたらちょっとテレビに出てる人ってくらいだろう。
「でも立派な人だよね。かっこいいよなあ」
しみじみと述べる。彼に対して常々感じていることだった。テレビで見る嵐山准は見るからに爽やかな好青年である。もしあれがよそ行きの顔ってだけで、彼のプライベートがとってもだらしなく粗悪な性格だろうとも、わたしは許してしまえるだろう。たとえ嘘でもあんなにキラキラ笑えるのってすごい。ニュースでの態度もコメントもしっかりしてるし、更には強い部隊の隊長だというじゃないか。並の人間ができることじゃない。並以下のわたしにはひっくり返っても真似できないと思う。同い年だからかはたまた身近な人間だからか、わたしはひっそりと彼への尊敬の念を抱いていた。うんうんと一人で頷く。大学生になったらあんなにしっかりしてないといけないものなのかなあ。無理難題を強いられているよ。
「そうだね、すごい人だよね」
「昨日のニュースに嵐山隊出てたよね」
「見た!」
「嵐山隊といえば木虎藍ちゃんの可愛さは何なの?」
「可愛いよね〜自分がババアに思えてくる」
「ほんとそれ。オペレーターの子も超美人」
「わたしは時枝くんがすきだ」
「じゃあサトケン!」
いつの間にやらわたしたちは嵐山隊をほめそやす会となったようだ。後援会だったのかもしれない。そういえばここに来る道では月末に控えるテストの話をしようって言ってた気がするけど、まあいっか。大盛り上がりの三人に水を差すことはしないで、わたしはにこにこ笑いながら眺めていた。
水曜日の明日はこのメンバーの誰とも会わない、魔のぼっち曜日だ。三人は水曜を全休にしたから、そもそも大学にいないのだ。……明日こそ、一人で食堂に行ってみようかなあ。思いながら、ストローでオレンジジュースを吸った。
|