|
本部でたまたま会った藍ちゃんがまだ制服だったので、軽い気持ちで「玉狛に行かないかい」と誘ってみたのだ。すると彼女は申し訳なさそうにこのあと防衛任務なんですと答えたあと、「何か用事があるんですか?」と問うた。礼儀正しい藍ちゃんは中等部からの先輩であるわたしに敬意を表してくれる。でもべつにナメてもらってもなけなしのプライドは傷つかないと思うからいいんだけどなあ。なんたって藍ちゃんは優秀なA級隊員なのだから。と一度地面に目を落として、それから彼女に向き直った。立派な用事じゃないよ。
「玉狛に気になる人ができたから会いに行きたくて」 「玉狛に…?」 「そう、同い年でね、かっこいいの」 「え」 正直に答えると藍ちゃんの表情筋が氷河期を迎えた。目をまん丸にして口角が引きつっている。大丈夫か、あなた。なんとなく顔も赤くなってるのは気のせいですか。いやはや、やはり藍ちゃんもわかっているのだろうか。わたしの気になる人は難攻不落の殿方であることを。そりゃあそうか、あの人なかなか、笑いすらしないものね。 「え、あの、それは、」 「うん、クールだよね。でもめげない!」 グッと拳を作ってみせたところで、腕時計の円盤が丁度いい時刻を報せてるのに気が付いた。防衛任務の入れ替え時間十分前だ、藍ちゃんそろそろ行かなきゃまずいよね。ということで、それじゃあね、と手を振って出口へ踵を返すと、藍ちゃんも遅れて振り返してはくれた。それがまるでさよならしたくなさそうで、わたしと別れ難いのかな?!と嬉しくなる。そんな自分の頭が大層めでたかったのだと気付いたのは、本部を出て五分ほど経ったあとだった。 もしかして藍ちゃんはとんでもない勘違いをしたのではないか? 玉狛への道のりでようやくそこに思い当たった。なるほど、そういえば烏丸くんも同い年だった。だから藍ちゃんはあんなに動揺してたのか。鉄壁のエリートなイメージなのに案外隙があるの、彼女のいいとこだよなあ。もしかしたら藍ちゃんは彼が十六歳であることをまだ知らないのかもしれない。 ……いいやそれにしたって藍ちゃん、仮にわたしと藍ちゃんが恋敵になったとして、藍ちゃんがわたしに負ける要素なんて一つもないでしょう。何を動揺したんだ。生きた時間の長さは、安心したまえ、そこに内包される人生の充実具合が藍ちゃんの大勝利だ。だからさっきも鼻で笑い飛ばしてくれて構わなかったのに。 ああでも、たとえそうだとしても複雑なのが乙女心なのかもしれない。わたしも他の子があの人のこと好きだって言い出したら、それだけでダメージくらうかも。いいやすでに、そんな女の子はたくさんいそうだ。 向こうの世界には。 彼女の期待には応えられず申し訳ないけれど、わたしの気になる人は近界民の捕虜くんである。 「暇な女だ」 開口一番に暇な女認定されてしまった。眉間のシワと鋭い眼光をオプションでつけられた上でのそれだ。ダメージはそこそこくらう。確かに大した用もなしに五回も玉狛に押しかけたら暇な女と思われても仕方ないのかもしれない。そりゃあできることならわたしだって、本部と玉狛支部を繋ぐ伝書鳩になって事あるごとに君に会いたい。けれど、残念、科学は発達し現在では電子通信というものが普及してしまっているのだ。こうして人と人とのコミュニケーションが希薄化し云々かんぬん。ところで今日もパーカーかっこいいね。「何も言わずに隣に座ろうとするな」駄目だったか。 「じゃあ上でおやつ食べよう、ヒュースくん」 「必要ない」 「バームクーヘンっていうね、買ってきたんだけど、おいしい洋菓子だよ」 ベッドに腰掛けてるヒュースくんの右手首を掴むとすごい勢いで振り払われた。ピシャリと叩かれた気分にさえなる。「気安く触るな」あ。ごめんなさい。明確な拒絶にうまく笑顔を維持できなくなる。やってしまった。まだ駄目だったかあー…ヒュースくんすごく嫌そうだ。 「あはは……ごめん」 「……」 「あの、ヒュースくん、でも、ほんとにおいしいから、」 「しつこいぞ」 「つきあってよ…」 ヒュースくんは初めて会ったときからこんな感じで、一ミリもわたしに心を許してなさそうな、氷を思わせる冷たさがある。それなのに気になって、会いたくなるわたしに問題があるのだろうか。ふと思ったけれど、その疑念がヒュースくんへの無関心と繋がることはなかった。 わたしはそこまで打たれ弱くないと思う。けど、このままずっと、何度会ってもヒュースくんに冷たくされ続けてたら、いつか泣いちゃう気がする。だって、ああそう、わたし、ヒュースくんのことすきになってしまったんだものね。人をすきになるとすぐに泣きたくなるって、本の中の主人公が言ってた。 「今回だけだ」 ハッと顔を上げる。ヒュースくんが大きな溜め息をついて腰を上げていたのだ。わたしより高い視点から目が合う。顔は変わらずしかめられていたけれど、どうやらわたしの悲愴具合に折れてくれたようだった。はあっと息を吸って、大きく頷く。別の意味で泣いてしまいそうだった。 地下からの階段を上がってリビングに行くと栞さんがお盆に二人分のバームクーヘンを乗せて運んでいるところで、わたしたちを見るなりおや?と口を丸くした。栞さんにはさっき顔を見せたとき、あとで部屋に持ってったげるねと言われていたのだ。それなのに二人でリビングに来たらどうしたのかと思われても仕方ないだろう。 「ここで食べてもいいですか?」 「いいよー。そろそろ陽太郎起きてくるかもだけど」 「ぜんぜん問題ないです!」 お盆を受け取ると栞さんはオペレータールームに引きこもると言ってリビングを出て行った。そういえば陽太郎くんは最近ヒュースくんにランク戦のログを見せてB級チームについて勉強させているらしい。わたしより陽太郎くんの方がよっぽどヒュースくんと上手にコミュニケーションを取れているようだ。いいなあ、わたしなんて未だに貴様呼ばわりだよ。そのヒュースくんはさっさと定位置(らしい)テレビ正面のソファに座り、何にも置かれていないテーブルに目を落としていた。ちっとも楽しみそうじゃないのが見て取れる。視界に入るようにバームクーヘンの乗ったお皿を目の前に置いたのはちょっとした反抗だ。 「……」 初めて見る扇型の造形に眉をひそめるヒュースくん。その横顔を眺めながら彼から見て左側のソファに座る。洋菓子はいくつか食べたことがあると栞さんに聞いた。その通りフォークの使い方に迷いはなく、彼は銀食器のそれを手に取り年輪に対して垂直に突き立てた。もしここに烏丸くんがいたら、一枚ずつはがして食べるのが正しい食べ方だって嘘教えそうだなあ。ぼんやりと思う。一口分切り取り頬張ったヒュースくんがかわいくて、わたしの口からそんな冗談を言う隙はなかったけども。 「おいしいでしょ」 「……悪くはないな」 簡潔な食レポである。おあとがよろしいようで。南無、と心の中で唱えて湧き上がる感動を鎮めることに集中する。わたし、こういう、ヒュースくんならこんなことでも幸せを感じるのだ。冷たくされ続けたら泣きそうになるけど、デレられすぎたら死んじゃう気もするなあ。なんだろう、ヒュースくん、すごいなあ。 自分が今までまともに人をすきになったことがないのが仕方なく思えてくる。だって十六年生きてきてようやくすきになった人、こっちの世界の人じゃなかったんだもの。 アフトクラトルとこちらの世界との異文化交流。運命の初恋の人は地球人の敵だった。近界という壁を超えた壮大な恋愛劇をわたしは、織りなしていくのだ。そんな歌が作れそう。わたしの頭の中では銀河がひしめいている。想像でしかない近界だ。わたしの恋はよりによって、すきだと口にするのすら躊躇われる。 「ヒュースくん、わたしの名前を知ってるかい」 「急に何だ」 すきだと言えない代わりに名前を呼ぶ。「って言うんですよ」だからヒュースくんにも呼んでもらいたい。わたしと同じ意図はなくとも、ヒュースくんに名前を呼んでもらえたらとても嬉しいと思う。真面目な話、ヒュースくんはわたしの名前覚えてない気がする。自己紹介はしたけど、睨むだけで興味なさそうだったから忘れてるだろう。今も十分睨まれてるけども。 「ずいぶんと上機嫌だな」 「え、えへ」 その通り、浮かれてる。というかヒュースくんといると大体いつも浮かれてる気がする。愚かな恋だと誰かに罵られる想像が容易いのに舞い上がってしまう。そういえばヒュースくんのトリガーは磁力を使うらしい。だとしたらヒュースくんはその磁力でわたしを引きつけてしまったのね。なんて、もしヒュースくんが言ったらキザすぎて笑ってしまうけれど。 むしろ愚かな恋だから浮かれてるのかも。わからない。こんな気持ち初めてなんだよ、ねえ恋の正解を教えてよヒュースくん。すきだよ。 アフトクラトルとの戦いの顛末はサラッと聞いただけでよくわかってない。よくわかってないわたしはそのことを考えるたび頭の中ではないちもんめが流れる。千佳ちゃんが欲しい、ヒュースくんが欲しい。それで、ヒュースくんがじゃんけんで負ける。ヒュースくんがこちらの世界に来る。勝って嬉しいはないちもんめ、負けて悔しいはないちもんめ。 そうヒュースくんはただの近界民じゃない。千佳ちゃんを連れ去ろうとして修くんが大怪我をして、C級隊員を三十二名連れ去った国の近界民だ。たくさんの人に恨まれているだろう。それなのにこの恋が上手くいくのか。 「」 少しぎこちない発音だった。この上なく喜んだのも束の間、ヒュースくんの能面のような表情と目が合う。自分のしたことで誰かから恨まれているとわかってて、それでもおびえてない顔だ。きっと後悔もしてないだろう。わたしはこういうときに、この人との強烈な次元の違いを感じていた。 「おまえはいつまでいるんだ」 「……」 それは、こっちのセリフだよ。言ってしまったら怒らせるかもしれなくて、口は一度噤む。名前で呼んでくれた。貴様じゃなくておまえって言った。嬉しいなあ、嬉しいのになあ。 「まだ」 下手くそに笑ってしまった。わたしはまだ帰らないし帰りたくない。ヒュースくんもまだ帰らないよね、帰れないんだよね?確認したくても聞けなかった。ここに来てしばらく経ってもヒュースくんは腰を落ち着かせてなさそうで、心は別のところにあるみたいで怖い。わたしへ敵意を向けることがなくなり、何の気なしに名前を呼んでくれるようになっても、ヒュースくんは何かの拍子に、簡単にいなくなっちゃいそうなのだ。 ヒュースくんはアフトクラトルに帰りたいのだろうか。わたしは君が欲しいのに。 手に持っていたフォークをお皿に置く。じわりと、視界が滲むのがわかった。すぐにぼたっと涙が零れる。恋をしたから泣いたんだ。ヒュースくんがそれを見て驚いたけれど、わたしもヒュースくんも適切な言葉が思い浮かばなくて、二人して黙ったままだった。 頭の中には広大な銀河が、皮肉にもまだひしめいている。初恋に舞い上がる女子高校生の運命の人は近界民だったよって話。 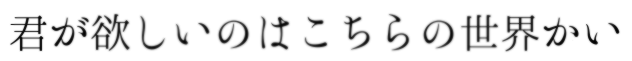 ねえ君、こっちの世界に絆されてくださいよ。こっちにずっといたいって思ってくれないかなあ。そしたらわたし、堂々と君にすきだと言えるんだよ。
「トイボックス」へ提出
|