|
入廷した途端浴びる視線を思い出し、気分はゆらゆらと低空飛行になる。行きたくないなあ……。
部屋の全身鏡の前に立ち、自分の姿をじっと見てみる。あれよあれよという間に着替えさせられたドレスは赤を基調としていて、腰に大きな黒いリボンのついた可愛いデザインだった。ウエストの切り替えしからふんわりと広がるスカートはふくらはぎまでを隠し、裾から伸びる足にはピカピカの赤いハイヒールがきっちりと履かれていた。右耳の上辺りにつけられたバラの髪飾りも真っ赤だ。 ぎゅうっとスカートを握る。いつもわたしが言う前に整えられる身だしなみはどう考えてもこのあとのことには適していない。だから今日も一人、鏡の前で難しい顔をせざるを得なかった。あの場でこんな派手な服装をしているのは自分だけで、反対に周りの人たちはみんな落ち着いた色の服を着ているからものすごく目立つのだ。わたしはそれが嫌だった。 ゆっくりと目を閉じて考える。……こういうところが駄目なんだよ。でも君にとっては、いいんだろう。 わたしが疑問を問い掛けるのはほとんど一人に対してだけだ。だからこの場違いなドレスコードについても聞いたことがある。すると彼はにやりと悪そうな笑みを浮かべて、「権力の誇示だ」と言った。そんな、納得したくない答えに反抗したところで結果は目に見えているから、このときも口を尖らせてすぐに話を終わらせた。いつもそうだ。 鏡から離れ、ふかふかのソファにぼすんと座り込む。スカートを踏まないように足を抱え込んだらハイヒールのせいで少し苦しかった。だからすぐに伸ばしてしまい、肘掛けに倒れこむ。すると今度は髪飾りが邪魔をするので、いよいよ鬱陶しくなって起き上がってみるけれど何をするでもなく、はあっと脱力して背もたれに深く寄り掛かるのだった。 だいたい、目立つドレスも髪飾りも、召使いに指示をしたのは彼だ。どれもこれも君の言う権力の誇示のためなんでしょう。思いながら、イヤリングに埋め込まれた赤い宝石を触る。するとなんとまあ、沈んでいた気分は次第に浮き上がってくるので、ふうと息を吐いてみる。不満は確かにあるのに、しかし実際のところわたしは赤い色が一番すきだし、綺麗に着飾られた自分もすきなので、だから全部言う通りにしようという気になるのだ。 もう少しで時間だ。迎えが来るまでここで待っていればいい。今度は大きく息を吸い込むと、タイミング良くスタスタと早歩きの足音が聞こえてきた。閉じられた入り口の方を見遣り、目をパチパチと瞬かせる。……どうしたのかな、足音が忙しない。 バンッと勢い良くドアが開かれた。予想通りの人物がそこから入ってくる。と同時に、なにやら甘い匂いが漂った。 「クソがッ!」 バタンとこれまた勢い良く閉めた真くんはものすごく不機嫌そうだ。何をそんなに怒っているのだろう。しかめた顔のまま見られてなんだか睨まれた気分になる。けれどさっきからやたらと香る甘い匂いが、彼の剣幕をいびつに緩和していた。「どうしたの?」外面のいい彼がここに来る前からあれほど歩調を乱すなんて滅多にない。問うと、一層ぎゅっと眉間に皺が寄ったのがわかった。 「時計ぶっ壊された」 「え?」 「あのイカれ帽子屋ども、やっぱ殺しとくんだったぜ…時間が止まって大人しくなるかと思ったら今度は茶会始めて好き勝手しやがって」 片手に握られていた彼お気に入りの懐中時計が怒りに任せて床に叩きつけられる。わたしからでも見えた、ジャムやバターをべったりと塗りたくられたそれが鈍い音で跳ねた瞬間、部屋中により一層甘い匂いが広がった、気がした。改めて鼻で大きく吸い込む。なるほど、これはストロベリージャムの匂いか。 帽子屋と三月ウサギは眠りネズミを交えて終わらないお茶会を開いている。随分前、初めて彼らをコンサートに呼んだ際きらきらコウモリという意味不明な歌を披露した帽子屋の時間を首切り役人が切り刻んでから、彼の時間は「ヘソを曲げて」しまい、午後六時から進まなくなったのだ。ずっと六時だからお茶会も終わらない。きっと真くんは、ここに来る前に三月ウサギの家の近くを通って見事絡まれてしまったのだろう。それは災難だったろうなあ、と思いながら、離れたところに立って手袋を外す彼をじっと見つめる。 「でも今回の証人なんだよね?」 「ああ。これであの口うるせえハートのジャックも処刑できる」 どうやら物に当たって気が済んだらしい。わたしと目を合わせた真くんは打って変わって楽しそうに口角を吊り上げていた。言いながら手袋を床に投げ捨て、棚の引き出しから同じものを取り出す。ここはわたしの部屋なのに、彼も私物を置いたり好き勝手しているのだ。べつにいいんだけれど。それよりさっきの人を殺しそうな顔はどこに隠しているのだろう。すっかり見えなくなったそれは、怖かったので思い出すのをやめた。 自宅から着替えてきたのだろう、裁判での役割に適したかっちりとした正装は恐ろしく真くんに似合っていた。白ウサギの彼は、証拠物件の提示や裁判を進行させる布告役だ。主張せず薄くなりすぎず、しかしここの支配者が誰なのかはっきりさせる黒のスーツにはさりげなく赤のハートがあしらわれていた。彼は「ハートの女王」の臣下だ。 「…楽しそうだね」 「ああ、そんなに暗くならないでくださいよ、女王さま」 「あなたが住みやすい世界にするために必要なことなんですよ」白々しい、薄っぺらい笑顔を貼り付けてのたまう白ウサギから逃れるように目を伏せる。よくもまあそんなことが言えるな。嘘つきめ。落ち着いていた気分は、また低空飛行を始めていた。 全部嘘だ。こんなことをして住みやすいのは白ウサギだけだ。女王の権力を利用して白ウサギにとって都合の悪い者をどんどん消しているのだ。おかげでわたしはあちこちから恨みを買い、いつ背中を刺されるんじゃないかと怖くて一人で外も出歩けない。母親が癇癪持ちですぐに怒っては打ち首を宣告していたものだから、娘のわたしまでそうだと思われているのだ。圧政をしく母の代から布告役を勤めていた真くんは幼いわたしにああはなるなと言い聞かせていたくせに、いざわたしに王権が降りてくると同じことをさせる。全部彼の指示だった。今回だって、わたしの作ったタルトなんてどうでもいいのに、それが盗まれたのをいいことにハートのジャックを処刑するつもりなのだ。 ふと、チェシャ猫に言われたことを思い出す。ついこの間、わたしの前に現れ、独り言のように、けれど言い聞かせるように口にしてすぐに消えてしまった彼の台詞だ。……本当にそうだ、でもわたしは違う、はず。 「そんなことより、おまえの懐中時計どこだよ」 「宝石箱の中」 「なんだまだしまってんのか」 「…うん」 何でも揃っているこの部屋は広い。大きな棚に引き出しの数は優に三十は越えていたけれど、わたしが言う前に真くんは棚へ目を滑らせ迷うことなく宝石箱のしまってある引き出しを開けた。彼はわたしについてすべて把握している。幼い頃からわたしの面倒を見ていたのが彼だったからだ。きっと真くんはいずれこうなることがわかっていたのだろう。ハートの王と女王が死に、その子供に王権が降りてくることが。 「ほら」 ぼんやりしていたら真くんが目の前にいた。唐突に差し出されたそれを受け取る。大粒のルビーが連なったネックレスだ。「つけとけ」見上げると、彼はわたしに目もくれず懐中時計の調子を見ているようだった。宝石箱の中から時計と一緒にこれを取り出したのだろう。言われた通りに自分で首裏に回し、カチリと金具を付ける。首元がひんやりと冷たい。なぞるようにそれに触れていると、時計から目を離した真くんはわたしを見下ろして、にこりと笑った。 「似合うよ、」 「………」それはずるい。わたしは君に不満ばかりなのに、そんなことを言われたんじゃ何も言い返せなくなる。悔しい。ぎゅっと口を尖らせ、口角が上がってしまうのを堪える。真くんは懐中時計の調子を確かめたあと、それをジャケットの内ポケットにしまったようだった。 懐中時計は真くんと同じものだ。絶対に正しい時間を示す代物で、使いやすいからと昔彼にプレゼントされたのだ。けれど時間の価値がわかるようになる頃にはわたしは外が怖くなり一人では出歩かなくなって、そうなると時間の管理を自分でする必要もなくなるので結果的に懐中時計は一度も使われず、大切な物を入れる宝石箱にしまったままになっていた。 もし、と思う。もしわたしが気軽に外を歩けたなら、懐中時計は存分に役に立っただろう。でもそれは、この先一度も実現しそうになかった。 「…時計、あげるよ。どうせ使わないし」 「おいおいスネてんなよ。ほんと裁判前になると情緒不安定だよな」 ああいつもか。馬鹿にしたように笑う真くんを睨みつける。しかしまるで物怖じしない彼はそのまま、スラックスのポケットにしまっていた手袋を取り出して優雅にはめた。白い仔ヤギの皮手袋で彼の準備は整う。わたしは、その動作がやけに綺麗だったもので、気分を害したのもすっかり忘れ見入っていた。 ぎゅっと握り込み完了した、と思ったら、その白い手がこちらに伸びてきた。ハッと我に返ったときにはすでに、真くんに抱きすくめられていた。 「おまえが何と言おうと、ここではハートの女王が正義だ」 彼の顔は見えない。呪文のように唱えられる言葉を、身動きの取れないわたしはただ享受するしかなかった。少しして真くんが離れても湧き上がった心臓は落ち着いてなかったから、多分顔にも出てしまっているだろう。彼の言うこととすることのギャップにはまだ慣れない。 「だからおまえは、俺の言う通りに断罪してればいいんだよ」整えられた髪が崩れないよう、優しく撫でられる。柔らかい皮手袋の感触からわずかに真くんの体温が伝わってきて、絶望する暇もない。満足げに笑う彼をじっと見つめ返すだけだった。 こんなことを思うのはおかしいかな。真くんといるとときどき、彼の行動原理が伝わってくる気がする。深い赤色の瞳はまるで、とても大切なものを映しているみたいなのだ。  判決が下されハートのジャックが処刑場へ連れて行かれる。溢れ返っていた見物人たちも閉廷となった途端、何食わぬ顔でぞろぞろと姿を消していっていた。役目を終えた俺も布告席から降りながら、証拠として使った紙切れを破きそこらにバラ撒いた。こんなものはもうどうでもよかった。いらないものはさっさと処分するに限る。 地面に着き法廷の正面を仰ぐと、一人玉座に座る女王の姿を捉えた。先ほどのことが思い出され、無意識に笑みが零れる。一切の躊躇も見せずに有罪を述べた女王は今回で更に周囲に恐怖を植えつけたことだろう。裁判が終わって気が抜けたのか、安堵している様子の彼女に下から声を掛ける。 「女王さま、帰りましょう」 女王は俺を視界に映すと一つ息をつき、「うん」小さく頷いた。 ハートのジャックがいなくなっていよいよこいつの側近は俺だけだ。先代の王と女王を反面教師に慎みを持てだの形だけの権力にしておけだのうるさかったあいつは今日晴れて首切り役人の厄介になる。やたら地位だけは高いあいつを処刑する機会をずっとうかがっていた俺としてはそれがようやく叶いだいぶ清々としていた。耳障りな声がなくなるだけで俺の生活は随分快適になることだろう。 があいつに入れ知恵されんのも面白くなかったしな。 周囲から孤立していくばかりの女王は臣下なんて片手で足りる程度の人数しか信用できていない。母親たちのように自分もふとした拍子に殺されるんじゃないかと怖いのだ。先代の女王が好んでしていた隊列は周りにいてほしくないからと廃止されたし、外には俺か、俺が指示した臣下としか出歩かない。法廷から城への帰り道もそういう理由で二人だけだった。 「今日は問題なく終わったな」 「うん」 「案の定帽子屋はクソみたいに使えなかったけどな」 「はは…そうだね」 まああのイカれ帽子屋と話が通じたことなんざそうそうねえがな。それより裁判の最中にチェシャ猫が出てくると決まって滅茶苦茶にされるからそっちの方が懸念事項だった。しかし今回は奴の登場もなく予定通り事が運び、裁判官である女王があらかじめ決められていた判決の言葉を述べ無事終わったのだった。 同じことを考えていたのだろう、が隣で「チェシャ猫が、」と呟いた。横目で見遣る。進行方向こそ見ていたが、随分と浮かない顔をしていた。 「この世界の人たちはみんな狂ってるって言ってた」 「ああ?キチガイ筆頭が何言ってんだよ。……つか、いつ会ったんだよクソ猫に」 「この間庭にいたときに」 「チッ…」 城の庭園はが一人歩きできる数少ない場所の一つだ。何を考えてるかわからないあいつとは極力合わせまいとしていたが、やはりあの神出鬼没猫相手に無理な話だったか。 思い通りにならないのはチェシャ猫だけじゃない。帽子屋と三月ウサギも意味不明な茶会を開き続けては進まない時間を謳歌してやがる。あのキチガイ共は何かしでかす前に処刑したいと考えてはいるが、チェシャ猫は追えないわ帽子屋共とは話が通じないわで未だ裁判に至れずにいた。 「もう会うんじゃねえぞ」 「無茶だよ…」 左右に林が広がる小道を歩いていると、前方の木の陰に気配を感じた。の手を引き立ち止まる。「わっ」よろけた彼女を気に留めることはせず、何者かの登場に身構える。しかし、ガサリと茂みを掻き分け出てきた奴らが誰だかわかった途端、一気にはあ、と気が抜けた。 「……おまえらか…」 「ハートの女王さまと白ウサギだ」「今日も一緒にいるんだ」 その声で、茂みの音にビビッて俺の後ろに隠れていたがおずおずと顔を出す。「…あ、トゥイードル兄弟」彼女が名前を呟くと、瓜二つのそいつらは軽快な動きで道のど真ん中に立ち塞がった。んだよこいつら……頼んだって遊んでやんねえぞ。 「ねえ女王さま、聞きたいことがあるんだけど」「今日は怒らない?」 「怒らないよ!」 が背筋をピンと伸ばして即答する。ついさっきまで権力にもの言わせて断罪してた奴がよく言うな。顔には出さず見下ろす。緊張気味の彼女は双子に対してもびくびくしていたが、できれば仲良くしたいのだろう、友好的な雰囲気を醸していた。だからそういうところがバカだっつってんだろ。普段そうやって温厚な態度見せるから癇癪持ちだとか二重人格だとか噂されんだよ。 ……ま、全部俺の言う通りにした結果だけどな。思いながら、双子がお互い顔を見合わせるのを眺めていた。二人は同時にこちらに向き直ると、ディーの方が口を開いた。 「二人は結婚するの?」 「……あ?」 あまりの素っ頓狂な問いに思わず声が漏れた。何言ってやがんだこいつら。思いっきり顔をしかめるが好奇心だけで聞いてくる双子は怯む様子もない。仕方なしにに目を向けると、「……女王さま…」そいつはまん丸に目を見開いて、顔を赤くして見事に固まっていた。おい、なに真に受けてんだよバカ。 「くだらねえこと言ってんじゃねえよ。女王さま、行きましょう」 双子に言い放ち、を促して通り抜けた。後ろでは何やら小さな声で話しているのが聞こえたが、振り返ってもすでに姿は消えていて追及は叶わなかった。舌打ちするとようやく我に返ったらしいがハッと顔を上げた。 「あ、び、びっくりした…」 「びっくりしすぎだろ。あんなんいちいち真に受けてんなよ」 「そうだよね、はは…」 苦笑いをするを見下ろし、それから進行方向に顔を上げた。自分の中に湧いてきたある種の感動は押し込めて、至って平然と歩を進めていく。……こんなんで喜ぶとかダセえマネするかよ。 女王の部屋に着きドアを開ける。俺が叩きつけた懐中時計やジャムの匂いは消えていた。「じゃあ俺は一回家戻るわ」入り口で立ち止まって伝えると、彼女はわかりやすく眉をハの字にして不安をあらわにした。恨みを買っている自覚のある彼女は一人でいることを心底嫌がる。裁判のあとは特にそうだ。いつものことなのでそのリアクションには慣れたものだが、慣れとは別に、おそらく俺はこの瞬間を一番楽しんでいた。本人目の前で口がにやけてしまうのを堪え、顔を逸らす。ついでに気を紛らわすため手袋も外し、ポケットに突っ込んだ。…さてどうするか。着替えるために帰るつもりだったからべつに急ぎでもねえし、こいつの気が済むまで部屋にいてやってもいい。 逸らした先の窓からは広い庭園が見下ろせる。何となく見遣ると、庭師が三人、せっせと赤いペンキを白いバラに塗りたくっているのが見えた。……へえ。思わずにやりと笑う。それはすぐにしまい込み、作り笑いを貼り付け女王に振り返った。 「でしたら女王さま、散歩がてら一緒に来ていただけますか」 「、うん!」 「庭でも通ってゆっくり行きましょうね」手を引いて踵を返すとは少しだけ頬を赤くして嬉しそうに笑った。周りの目もないのに敬語を使う俺を不審に思わないほど一人でいたくなかったのだろう。そのせいでこれから死刑宣告をすることになるなんて、こいつは微塵も思ってねえんだろうなあ。 「こないだ庭師に頼んだら、赤いバラ植えてくれるって言ってた」 おそらくさっき言っていた、チェシャ猫と会ったときの話だろう。ああそうそう、チェシャ猫ね。あいつの言うこともあながち間違いじゃねえよ。ここではどいつもこいつもキチガイだ。俺もおまえも大概マトモじゃない。だが、そんなことは大した問題じゃなかった。 おまえだよ、。思いながら、じかに繋がる手を握り直す。 権力なんざ手段でしかない。俺はおまえが孤立して、俺なしで生きられなくなればいいと思ってんだよ。 女王が断罪するたびにそれは近付く。「楽しみだな」目を細めて笑うと、はこっちをじっと見上げていた。  ……やっぱりこんなことを思うのはおかしいかな。その目に映っているのは、いつもわたしだけなのに。 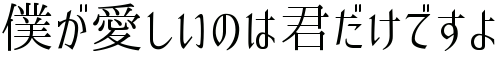 企画「ちいさな童話」様へ提出 |