|
※一年くらい未来の設定。捏造※ 夜の川というのは昼間と全く違う顔をしている。黒くうねる波を見て、その川面より彼方上、頼りなく夜空に貼り付く細い月を見上げる。水面を照らすような力もないその弱々しい月光を睨みつけて、吐いた息は煙の匂いがする。匂いの元を足元に落として、スニーカーで踏み躙ると、隣から「ポイ捨て反対」と声がかかった。 「桐絵」 「そんなの吸ってるってバレたら謹慎よ」 「別にいいよ」 喫煙は脳卒中の危険性が、等と長々と書かれたソフトケースをライターと一緒にポケットに突っ込む。このくらいの違法大したことない。この国には地球外の危険な場所に未成年を送り込む組織があるくせに、今さら未成年の少しの喫煙でがたがた言われる筋合いもないと思う。 桐絵は呆れた顔でため息をつくと、ポケットからロリポップをひとつ取り出して私に差し出してくれた。大人しく受け取って包装を剥がす。隣でも同じようにロリポップの包み紙を剥がす微かな音が、川の波音と混じり合って聞こえた。青い包み紙から現れたのはこれまた青い飴で、口に突っ込むとソーダのべたっとした甘みが広がる。 隣の人の影がぐっと伸びたと思ったら、彼女は川とこちらを隔てる柵の間に突っ込んだ足で一番下のポールに乗っかり、子どものように腕を突っ張って遊んでいた。自分のほうはやさぐれて、むしゃくしゃしてタバコを吸うなんて、それこそが子どもの証のような気もして、遣る瀬無い気持ちになる。 そのまましばらく二人して川面を眺めながら、口の中の飴を小さくする作業に勤しんだ。 「謹慎になったら困るくせに」 「困らない」 揶揄うような口調で徐に口を開いた桐絵は、だいぶ小さくなったロリポップをふらふらと揺らした。街灯の光を受けてきらっとするそれは赤い色をしている。イチゴだろうか。返事をするために取り出した私のほうの飴はまだ桐絵のものよりも大きい。 「困らないよ」 桐絵が返事をしないので、もう一度念を押すように言う。ちっとも困らない。ボーダーのほうで謹慎処分にされても、学校のほうで謹慎処分されても、どちらも構わない。だってそうだ。もうすぐ、彼女は。 「だって行ったって桐絵がいないんだもん」 笑われるかと思ったけど、桐絵は笑わなかった。困った顔をするでも怒るでもなく、ただただらしくない静かな目でこちらを見つめてくる。つぐんだ口からはロリポップの白い棒がぴょこんと突き出ていて、そこだけが場違いに間抜けだった。視線で私の顔に穴が開きそうだ。 目をそらすのを誤魔化すように飴をもう一度口に入れる。眺めていると、川の向こうに並ぶビルの窓の明かりがひとつ消えた。 「……ごめん」 謝られるとは思わなくて、びっくりして振り向いてしまったけれど、隣の彼女とは目が合わなかった。珍しく自分の後ろ頭をかくように髪をかき乱している。色素の薄いキャラメル色の長い髪が、夜風に舞う。 桐絵は優秀なアタッカーだ。私なんかとは比べ物にならないくらい経験を積んでいて、積んできた経験に値する、いやそれ以上の力を持っている。だから、高々三年程度の付き合いであっても、彼女がいつかこうして――遠征に発つ日が来ることは容易に予想できた。桐絵は明日、遠征に行ってしまう。 たかが遠征だ。何も帰ってこないわけじゃない。現に今まで遠征に行ってきた人も、成果を上げてきちんと帰ってきている。 ごりごりと夜の静けさの中にくぐもった音が響いて、いつの間にか寄っていた眉間のしわが緩んでしまう。桐絵は最後までおとなしく飴を舐めることができなくて、大抵途中で嚙み砕いてしまうのだ。 「」 なんと思ったのかわからないが、人の名前を呼びつけておいて、桐絵はちょっと肩を揺らして笑った。感情の読めなかった緑色の目が緩む。 「心配しすぎ」 「……心配くらい、する」 ほんとはただ彼女の心配をしているだけじゃない。 私には桐絵という友人を得てから、なんだか彼女いつの間にかどこかへ行ってしまうようなそんな根拠のない不安が心のどこかにあった。同じ学校で、同じボーダー隊員で、贅沢なほど桐絵との接点を持っているのに、どこか彼女は私と生きる世界が違うような、そんな不安だ。あまりにも馬鹿馬鹿しくて、あまりにもペシミスティックで、口に出してしまうと自分自身厭きれてしまいそうなので、そんな不安、桐絵にも誰にも言ったことはないけれど。 「ちゃんと行って帰ってくるわよ、あたし強いんだし」 「うん……」 「約束する。ね、指出して」 ロリポップの棒を持つ指先とは反対の手が差し出された。華奢な小指だけがぴんと立っていて、何をしたいか明白だったので、私は「いやだ」と拒否した。「なんでよう」と桐絵の眉があっという間に下がる。 「……夜中に指切りすると親の死に目に会えないんだよ」 「えっ、嘘っ、どうしよう」 私の、適当に迷信をアレンジした嘘にも気づかず桐絵がおろおろするので、笑って「嘘だよ」と言ってあげた。途端に桐絵が安心したように怒り出す。 ――指切りはしたくなかった。万が一にも、桐絵を嘘つきにして針千本なんか飲ませたくないからだ。 空高く浮かぶ細い細い三日月が、誰かが笑う目のようだった。 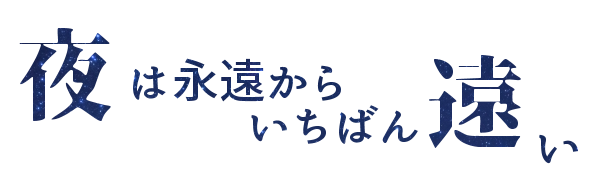
(18/08/04) title :エナメル / image :写真AC |