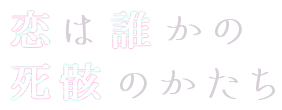
「藍ちゃん、さかむけ、痛くないの?」
がくるくるとペンを回しながらそう言うので、私もノートを書く手を止めた。
今日はボーダーの仕事の都合で休まなければならなかった授業の補講があって、私たちは土曜日のひと気の少ない学校に登校していた。ボーダーとは全く関係ないも、なぜか一緒に。
補講が終わって帰り支度をしようとしたのだけれど、が「藍ちゃん帰っちゃうの……?」と空欄の多いプリントを机の上に広げたまま、子犬のような目で私を見上げてくるものだから、私はまだ教室にいる。
プリントは、教師が「これを解いて提出したら帰ってよろしい」と補講の時間の最後に、私たちに配ったものだ。難しい内容でもないそのプリントを、数少ない補講メンバーの他の子たちはとっとと解いて下校してしまった。私は昼十二時を指そうとしている時計をちらちらと見ながら、ノートを開いて先ほどの補講の復習をしている。
「ああ……これのこと?」
「うん。痛そう」
昨日から右手の薬指のつめの横がさかむけになっているのだ。それをは指摘したいらしい。まるで自分の指がそうであるかのように、彼女は痛そうに顔をしかめて見せた。
「大したことじゃないわよ。それより、もう解き終わったの」
「う……まだです……ねえ、藍ちゃん~」
「代わりに解いたりはしないわよ。今日の復習の内容じゃない。簡単よ」
「うう……」
言えば、はうめきながら俯いて、ペンを回すのを止めた。カシャンと彼女の指先からゆっくりペンが落ちる。藍ちゃんの色、と言いながら私に先週お披露目してきた、新品の赤いシャープペンシル。
むむ、とうめくものがもう一つ。補講が終わってから机の上に取り出した、のスマホだ。液晶がパッと明るくなってなにかのメッセージを受信している。
「、なにか来てるよ」
「うう……なに……」
彼女はペンを手放した手で、そのスマホを取り上げて画面を一瞥すると、何の操作もせずにスマホを再び机の上、プリントの傍らに置いた。今度は液晶が下になるような向きで。彼女の、その画面を一瞥した目があまりにも冷えていた。私はそっと教室の時計を仰ぎ見る。とうとう短針と長針がそろって天を指してしまっており、正午になっていることを示していた。
が例の子からの連絡を、近頃少し面倒がっていることに私は気付いている。私が気付くくらいだから、当人はもちろん察しているだろう。それで連絡の頻度を控えるような子だったならまだしも、その子は逆のタイプだったようで、もっと連絡の頻度を上げてしまっているようだった。おかげで今のように、が届いたメッセージをそっと無視するのを目撃するのも多い。のそういう顔を見ると、私はつい心の片隅で「見たくなかったな」と思ってしまう。
「そういえば今日、どうしても補講なの」
「うん? 先生に言ったの」
再びペンを取って、ようやくプリントに向き合い始めたのつむじに向かって訊ねる。彼女は視線をプリントに落としたまま、こともなげにそう答えた。
「なにを言ったの? 授業休んでないのに補講って、よっぽどじゃない」
「先生に、藍ちゃんが受けるなら一緒に受けます~って私が言ったら、邪魔しに来ちゃダメって言われたんだけど、でも勉強するなら来ていいよって言われたの」
カリカリとようやく彼女がHBの芯でプリントの空欄に回答を書き記す。見たところ、正しい内容を書き込んでいるようだった。
「私が来るならって……」
「だって藍ちゃん休んじゃうんだもん。藍ちゃんに会える日が減っちゃうから、補講で補わないと」
何故か急にプリントを埋めるモードになったはプリントから顔をあげない。当たり前のことのように言うは、当たり前のように次の空欄にも回答を書き込んだ。すらすらと正しい解が書かれていく。まるで、最初から迷っていなかったみたいに。
「ねえ、藍ちゃん、この後ボーダーのお仕事?」
「今日は夕方からだけど……」
「じゃあ、お昼ごはん一緒に食べに行こうよ。藍ちゃんどこ行きたい?」
むむ、とのスマホが再びうなる。彼女は完全にそれを無視して、プリントに答えを書きつけていく。先ほどと違って、のスマホが何を受信しているのか、こちらからはうかがい知れない。
「、返事をしないの?」
お昼ごはんの問いかけに答えず、私がそう促すと、はムと唇をとがらせて黙り込んだ。教室の前を誰かが上履きを鳴らしながら遠ざかってゆく。
「いいの。今は藍ちゃんといるんだから」
彼女はスマホを隠すようにして机の上から取り上げると、机の横に掛けていた鞄のポケットにいささか乱暴に押し込んだ。誰からの連絡なのか、なんて彼女のこの態度だけで聞くまでもない。
「……喧嘩でもしてるの?」
「んー? ふふ、藍ちゃん心配してくれるの?」
つい一瞬前まで拗ねたようにとがっていた唇を、嬉しそうにほころばせて、彼女はペンケースにシャーペンと消しゴムを片付け始めた。見れば、プリントの空欄はすべて埋まっている。
「心配っていうか……」
あの子――メッセージの相手とがいわゆる〝お付き合い〟を始めたのは、先月のことだ。告白されたから、とは話していたし、実際にあの子とが並んで歩いているところも見たことはある。てっきり、これでが私に構ってくる時間も少なくなるだろうと、そう思っていたのだけれど、予想に反しては今まで通り私と一緒に居たがった。私と一緒にいるときは、いくらあの子から声を掛けられようとも後回しにするし、反対にあの子とが一緒にいる場面に私が通りがかろうものならば、「藍ちゃん」とはなぜかあの子を置き去りにして、私の方に駆け寄ってきてしまう。
「私は、」
はすごく優しい子だ。いつだって他人であるはずの私の幸せを優先して、だけれども、その優先が押しつけがましくなくって、それがすごく心地がいい。そういうしか私は知らなかった。先月までは。
なのに今のはなんだか違う。が私以外の――つまるところあの子に、そういう知らない態度をとるのが、今まで私が見たことのなかったの〝不誠実さ〟を浮き彫りにしているようで、そんなものは知りたくなかったと、心の中の身勝手な部分がそう言う。それと同時に思うのだ。それこそ、が私を好きでいてくれていることの証左なんじゃないかと。そう思う自分の方こそ不誠実のような気がして、身体の真ん中を冷たい手に握られたような心地になる。
私が視線を机の上にさまよわせていると、彼女が仕舞いかけたペンケースをもう一度開いた。中から何かを取り出して、私の視線の先に、の指先がそれを差し出す。ありふれたばんそうこうだ。
「藍ちゃん、さかむけに貼って。痛そうだから」
顔をあげると、は何でもない顔をして私を見ていた。いつの間にか、机の横から鞄を取り上げて肩に掛けている。
私がの顔を見つめ返して、何も動かないでいると、「藍ちゃんってば」とは笑って机の上の私の手を取った。あ、と思う。私より体温の高いの指先。
「ほら、貼ったげる」
肩に鞄を掛けた、不自由そうな格好のまま、いとも簡単にばんそうこうを私の指先に貼っていく。の手は私よりも指が長くて、爪も広い。あっという間に私のさかむけをばんそうこうで覆い隠したは、まだ呆けたように何も言わない私を見て、肩を揺らして笑った。
「藍ちゃん、なに食べる?」
はいつも嬉しそうに私の名前を呼ぶ。だけ、他の人の倍以上に私の名前を呼びたがるような気がする。彼女の口にする〝藍ちゃん〟が私を私から遠ざける。彼女が鞄に仕舞ったスマホが、まだあの子からのメッセージを受信しているのかどうか、私には知りようがなかった。
(21/01/24)
title:徒野