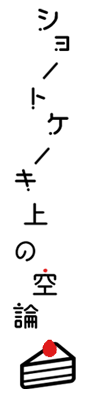
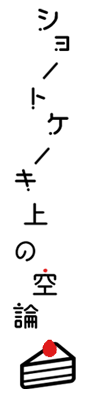
△
「華ちゃん、おはよう」
翌朝もは懲りずにやってきた。今度は隣の席を乗っ取って。ホームルームまで読もうと思っていた本を鞄から取り出す間もなく、少し離れていた机を寄せてくる。無論その席ものものではない。
「おはよう」
「はい」
「……これは?」
はブレザーのポケットからいくつか小さな飴を取り出して、机の上に転がした。小気味良い音を立てて散らばったそれを、華は昨日と同じように判然としない気持ちで見つめた。は大げさに首を傾げる。
「あめだよ?」
「それは見れば分かるわ」
同じ会話が繰り返されている、と思いつつ、華は飴を指でつまむ。苺の模様が散りばめられた白いワックスペーパーに飴が包まれ、両端を捻って留めてある。ふわりと甘酸っぱい香りが漂う。
今度はクラス中に配っているという訳ではなさそうだった。どうやらは自分に興味を持っているらしい、とさすがに華も気がついて、嬉しいでも厄介でもなく、物好きな、と感想を抱く。昨日の会話で彼女の関心を引くようなことがあったとは華には思えなかった。
「それね、好きなやつなんだ」
「あなた、いつもお菓子持って来てるの?」
「うん」
「そう……ありがとう」
呆気に取られて礼を言うのを忘れていた、と、取って付けたように付言すると、ふにゃりと崩れるようにが笑った。やわらかいスポンジケーキが、ほろほろと倒れるように。
華は無意識に目を逸らした。吸った息が熱を持ったような、何故か、肺を圧されたような気がして。誰にも触れられてはいないのに。
机の汚れを無意味に眺める華に気を留めず、は机に投げ出されたままの飴をひとつぶ拾い上げて、まるで情緒なく引き開けると口の中に放り込んだ。くれたんじゃないのか、と思ったが、元はのものだ。華は唇の裏側を柔く噛んで黙っていた。
おそるおそる目を上げるとは先の表情をほどいていた。理由も分からず華がほっとしていると、またがポケットをごそごそと掻き回し始める。今度は何が出てくるのだろう、まるでメリー・ポピンズの鞄みたい、そう思って華は僅かに緊張を解いた。
探り当てた何かをが取り出す。手のひら大のチューブだった。ほぼ白と言っていい、薄いベビーピンクのパッケージに赤い蓋。どうやら食べ物ではなさそうだった。くるくると蓋を回して開けると、チューブの腹を押して中身を手の甲に押し出した。ハンドクリームだ。先程の飴よりも濃く、強い香りが、途端にの周りを取り囲む。
「……すごい匂いね」
「あ、ごめん、いやだった?」
「いいえ。大丈夫」
思わず声にした言葉は、どちらも華の本心だった。しばらく消えないであろう甘い香りは、人工的なものだったが、不思議と不快には感じなかった。
手にクリームを擦り込みながらがチューブに描かれた絵を見せる。そこには苺の乗ったケーキが描かれていた。
「これ、ショートケーキの香りなんだって。すごくない?」
「そんなものまで甘いものなのね……」
「お菓子食べちゃいけないときとかに塗る」
「なる、ほど」
なるほどと言ったが華には良く分からなかった。は神妙な顔つきで爪の周りを馴染ませている。
言われてみれば、バニラのような香りがする。ショートケーキの香りとは、と華は悩みかけたが、こういうものはリアルに再現することは重要ではないのだろう、とすぐに考えるのをやめた。イチゴ味、と書かれた飴玉も、実際の苺の味はしない。
「華ちゃんもいる?」
「え、」
自分の手を塗り終えたが、チューブを示して小首を傾げる。華は反射的に自分の手を見た。色味のない、地味な手袋。その下に隠された自分の手。思わず言葉に詰まる。
はぱちんとまばたきをして、華が凝視するその両手を瞥視した。華もその気配に気付いたが、発する言葉も、すべき行動も思い付かず、ただ自らの手を見つめた。
すると突然その視界にの手が伸びてくる。は、と気が付くと、が華の腕を緩く握っている。状況が飲み込めず、華はそれを目を丸くして見ている。が華のブラウスの袖を数センチ捲ったところで、華はきゅっと身体を硬くさせた。
しかしは手袋には触れず、予め指に取ってあったハンドクリームを、そっと華の手首に乗せた。の指が、するりと華の手首を撫でる。
「……っ!?」
「あ、ごめん、冷たかったよねえ」
そういうことではない。吐き捨てたい気持ちがいっぱいに広がったが、声にならずに腕を胸に引き寄せた。は手を振り払われてもにこにこと嬉しそうにしている。触れられた手首から背中までざわざわと落ち着かない。の指はもう離れているのに、皮膚に何か触れているような感覚が抜けないのだ。
華が透明な触感と戦っていると、は呑気に手のひらを顔に近付けて見せた。
「ね、いいにおいでしょ」
顔を覆うようにしていた手のひらを、ぱっと外側に向けて、彼女はまたふうわりと笑った。華は、まだ白いクリームがうっすら残った自分の手首に視線を落として、逡巡したが、がしたように鼻先に近付けた。
そんなことをしなくても、十分この(ショートケーキらしい)香りは辺りを満たしていたが、それを見てはますます嬉しそうに目を細める。
華は遮るようにまばたきをして、残ったクリームを擦り込んだ。
「わたしにはちょっと甘すぎるわね」
「えー?だめかあ」
「でも」
あなたには似合うんじゃない。雫された言葉に、がどんな表情をしたのか、顔を背けたままの華には見えなかった。
ただ机の上に転がされたままの飴を手に取って、また幼馴染みに奪い取られるのは少し惜しいと思い、包みを開いて口に放り込んだ。イメージ上の苺の味で、本物の苺の味にはやはり遠い。でも、嫌いじゃない、と華は思う。
甘いだけのクリームの香りに、この甘酸っぱい苺の香りが混ざれば、少しはショートケーキらしくなるのでは、とも思ったことは、何故だかには言えなかった。