|
昔からよく見る夢がある。 私はひと気のないビルが立ち並ぶ見覚えのない街並みの中で、息を殺して潜んでいる。天候は曇天で、今にも雨が降り出しそうな空気だ。誰かが機械越しに私に話しかけてきて、私はそれに軽く頷く。手にした何か――未だにそれが何なのかわからない――を握り直して、意を決して物陰から飛び出そうと腰を浮かせると、道の向かいで同じように潜んでいた誰かと視線がぶつかった。あちらがニッと楽しげに笑うので、私もにっこり笑う。不思議と理由もなくそれが私の敵ではなく味方なのだと私はわかっている。 いざ、と足を一歩踏み出したところでいつも夢から醒めてしまって、結局夢の中の私が何をしていたのかいつも分からずじまいだ。 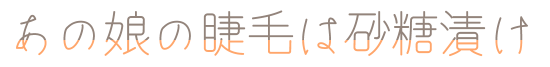
市街地のショッピングモール内、昼下がりの某有名コーヒーチェーン店の店内は込み合ってていた。 注文した飲み物を手に、空いているテーブルを探して店内をぐるりと見渡すと、見覚えのある姿をカウンター席に見つけた。ちょうどよく隣の席が空いている。 「葉子ちゃん?」 考える前に声をかけてしまっていた。 くるんとこちらを向いた彼女の顔は記憶にあるより少し大人っぽくなっていて、なんだか妙にどきどきしてしまう。返事をしてくれるかどうか一瞬で不安に駆られたが、私の心配に反して葉子ちゃんは「……久しぶり」と答えてくれた。 「久しぶり! ねえ、隣座ってもいい?」 「空いてるから、いい」 「ありがとう」 葉子ちゃんはカップケーキと飲み物の入ったカップをカウンターに並べて、手の中のスマートフォンの画面に視線を落としていた。傍にある荷物から察するに、お買い物に来ていたらしい。 「葉子ちゃんはお買い物?」 「まあね」 そっけないながらも答えてくれる葉子ちゃんに心の中で苦笑する。思えば、中学時代もそうだった。私は葉子ちゃんの親友の華ちゃん――染井華ちゃんと中学で三年間同じクラスになって、華ちゃん経由で葉子ちゃんと知り合った。華ちゃんと親しい私に対して葉子ちゃんがどう思っていたのか、正直なところあまりよく思っていなさそうだった。葉子ちゃんとは、中学校から華ちゃんと一緒に帰る道中で遭遇するのが大抵だったが、にっこり笑う葉子ちゃんを私は見たことがない。 そんな葉子ちゃんともこうして会うのは本当に久しぶりだ。中学卒業以来だろうか。 そもそも華ちゃんがいる場でしか話したことがないので、正直思わず声をかけてしまって、無視されないか心配だった。それはさすがに杞憂だったけれど。 「そっちは?」 「本屋さんに来て、ついでに休憩」 「ふーん」 興味がなさそうな返事が返ってきて、彼女は手元のカップに口をつけた。この薄い反応も懐かしく感じてしまう。華ちゃんを介さずに葉子ちゃんと会話らしきものができたことに、感動すら覚えつつ私も買ったアイスコーヒーを一口飲んだ。 「……華と」 「えっ?」 アイスコーヒーよりもなんとかフラペチーノにすればよかったかなあ、と窓ガラスの向こう側の見るからに暑そうな青空に目を細めていたら、隣から思いがけず話しかけられて咄嗟に聞き損ねてしまった。問い返してしまった私の声に、葉子ちゃんがむっとした顔をする。美人はどんな顔をしても美人だけど、私は葉子ちゃんのこのパターンの顔ばかり見ている気がする。 「ごめん、なに?」 「……華と同じクラスなんでしょ」 「あっ、うん、うんそうなの。また同じクラス」 中学三年間同じクラスだった華ちゃんとは同じ高校に進学した。その上、余程縁があるのか、また同じクラスになったのだ。同じクラスに知り合いが全くいなかったらどうしようと心配していたところにこれなので、入学早々浮かれたものだ。華ちゃんも分かりにくいながら喜んでくれていた、と思う。 「葉子ちゃん、てっきり華ちゃんと同じ高校に行くんだと思ってた」 だから入学して、華ちゃんの隣に葉子ちゃんがいなくて驚いたものだ。葉子ちゃんはふふんと笑うと、カップケーキに噛り付いた。チョコチップがひとつ、ケーキの小さなカケラと一緒に皿に落ちる。 「アタシはね、同じ学校で四六時中一緒にいなくっても平気なの」 得意げにそういう葉子ちゃんに思わず頬が緩んでしまう。葉子ちゃんの強がりというか、見栄というか……自信かもしれない、そういうものが垣間見えると、なんだかいつもほほえましくなってしまうのだ。 「そっか、仲いいもんね」 「当たり前でしょ。……あんたは?」 「えっ?」 何を訊ねられたのか分からなくて問い返してしまうと、葉子ちゃんが急に言葉に詰まったように眉を下げたので、私は急がせるつもりはないポーズのつもりで手元のアイスコーヒーを飲んだ。 店内には空調が効いているので話している間にコーヒーがぬるくなっていることもない。少しの間沈黙が流れて、カップについた結露で濡れた指先をすり合わせていると、葉子ちゃんがようやく「は、」と口火を切った。 「最近……その全然見かけなかったけど」 「うん、そっちこそ」 「あ、アタシは忙しいから……その、そうじゃなくって」 忙しいのは実は知っていた。華ちゃんもボーダー隊員で、葉子ちゃんもそうだって聞いていたから。 「あ、気にしてくれたの? ありがとうね」 「気にしてはない! 気にしてないから!」 きゅっと眉を吊り上げて葉子ちゃんが噛みついてくるけど、私はちっとも気にならなかった。 中学時代の三年間くらいを軸にした経験則だけれど照れてるんだろうと分かるから。葉子ちゃんは結構分かりやすいところがある。中学卒業して……三か月くらい。私に会わなくなったことになんて気にしてないどころか、気づいてすらいなくても無理はないなと思ったのに、彼女は意外と気にしてくれていたらしい。 「私は元気してたよ。葉子ちゃんに会わなくなったから、華ちゃんと一緒でボーダーのお仕事忙しくなったのかなって思ってた」 葉子ちゃんはちょっと驚いたみたいで、その形のいい唇をぽかんと開いて私を見た。ぱちぱち瞬きをする目を縁取る睫毛すら綺麗だ。 「……ボーダーのこと、知ってたの」 「あっ、ごめん華ちゃんから聞いて」 葉子ちゃんは「別に」と視線を落とすと、いつの間にか空になったカップのストローを弄んだ。 「なら、構わないわ」 「そ、そう? ありがとう」 外は眩しいくらいの青空なのに、なぜだか不意に今朝の夢で見た曇天を思い出した。あの時、向かいにいたのは――なんの前触れもなく点と点が繋がりそうな、気がする。 「」 隣でガタン、と鳴った椅子の音が思考を断ち切る。結びつきかけた何かは結局またうやむやになってしまった。 「アタシもう行くから」 「あ、うん。またね」 「また……ねえ、」 カウンターの上のスマートフォンを掴む彼女の指先が、迷うように画面を滑る。私は、仕方がないなと少し笑った。 「葉子ちゃん、連絡先教えてよ」 葉子ちゃんの言葉の先回りをして自分のスマートフォンを取り出した私の選択は間違いじゃなかったらしい。言葉をさえぎられるかたちになった葉子ちゃんが、怒りもせずにニッと笑う。綺麗な弧を描いた唇に、今度こそ夢の中の一つの点と点が繋がった。そうだ、あの時、向かいで笑ってくれたのは。 (18/07/29) title :約30の嘘 |