次の約束は死なないでと言っていたんだろう。
「あ、鳩原ちゃん」
隣を歩く犬飼の声だった。その声音といえば草花の周りを浮遊するモンシロチョウに対する「あ、蝶だ」と同じような覇気のなさに薄ら笑いをオプションし、心の中は何を思っているのかてんで読めない、そんな普段通りの師匠の声だった。同学年で使用武器が同じだったのを理由に弟子入りし、あれは確か二度目の特訓前の出来事だった。読めない師匠に尊敬と畏怖の感情でどう接していいかわからなかった頃だ。
その読めない犬飼がやっぱり読めない声で呼びかけた彼女、鳩原未来さん(のちにわたしが「鳩原さん」と慕う人物である)は気付くと向かいから歩いてきていた足を止め、犬飼に対し物怖じすることもなく「あ、」と顔を上げた。猫背なのだろう、人と対面することにより少し背筋が伸びたのがわかった。
「今日来てたんだ」
「うん。の特訓で」
こちら、というように上品にも指を揃えた手のひらを上に向けわたしを指した犬飼に気を配る余裕もなく、わたしは目の前の鳩原未来さんを見上げていた。背はわたしと同じくらい?真っ黒の髪の毛は毛先が跳ねている。眠そうに目を瞬かせたと思ったら逸らされた。あ、人見知り。それに気付いてしまいわたしも目を逸らした。気を遣ったんじゃなくて、気付いてしまったこと自体に申し訳なさを感じたのだ。何を隠そうわたしも初対面の人はあんまり得意じゃない。
「こんにちは…」
「あ、こんにちは…」
見事なほどよそよそしく会釈をした二人を間近で見ていた犬飼が早々にその場を切り上げた判断は正しかっただろう。今となっては、彼に「鳩原ちゃんに師匠を変わってあげたい」と言わしめるほどになったけれど。
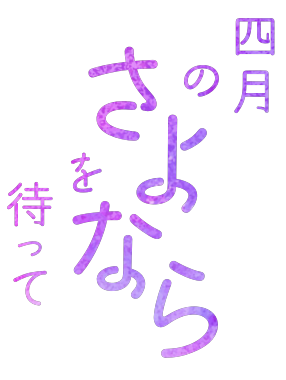
「変じゃないかな」
後ろでしばった髪の束をべっこう飴みたいなヘアゴムで結んだ。初の試みだった。これを買ったのは例に漏れず鳩原さんと一緒に出かけた隣町の洋服屋さんだ。うんうん唸って、最終的に鳩原さんが一番似合うと言ってくれた、中にラメがキラキラ入ったカラメル色のヘアゴムを買った。鳩原さんが一番似合うって言ってくれたら間違いない。だってわたしは鳩原さんに一番に褒めてもらいたい。次遊びに行くときつけてくるねと言えば、「楽しみだなあ」と緩やかな笑みを浮かべた、あなた。幸せ。
「変じゃないよ」
「よし」
「ねえおれ鏡じゃないんだけど」
ボーダー基地の壁に寄りかかる犬飼はコテンと首を傾げた。その声はちょっとめんどくさそうにすら聞こえた。この春高三に進級した今となっては師匠である犬飼のこともなんとなくわかってきて、彼への感情は炊飯器程度の義理と糸唐辛子程度の信頼で構成されていた。わさわさと自分の後頭部につけた髪飾りをいじっていた手を止め、ゆっくり離す。たまたま見かけたから声をかけて、真後ろがどうなってるか聞いただけだ。
「知ってる」
「だよな」
「…これから鳩原さんと出かけるの」
「知ってる」
「だよね」
ちょっと面白いやり取りをしたけどどちらからともなく笑い出すなんてことはなかった。犬飼が懸念している通りわたしは犬飼のことをちょうどいい友人だと思っている節があるので鏡みたいなことに使ってる。犬飼のセンスは信頼できるのでコーディネートの助言をもらったりしている。犬飼も嫌そうな顔をすることはなく、毎回わたしがジュースをおごるだけで了承してくれる。もちろん、犬飼のセンスより優先されるのが鳩原さんの好みなのだけど。
「って自分がすきなの?」
そんなことを聞かれたのは初めてだった。内心驚いて目を丸くする。犬飼はわたしをいじろうとしてるのではなく至極単純に、「って焼肉がすきなの?」と同じレベルで、ふと思いついたから聞いてみたというようにわたしを見ていた。
「なんで」
「だって鳩原ちゃんとってちょいちょい似てるじゃん。自分みたいだからすきなのかと思って」
褒め言葉?よほど言ってやりたかったけれど相手は犬飼だ。冗談を言って笑い合う仲じゃないのは重々承知してる。だから冗談じゃない。犬飼も冗談言ってない。
似てない、口にして絶望した。絶望した理由もわからなかった。わたしは鳩原さんになりたかったのだろうか。鳩原さんと話すようになって鳩原さんとお出かけするようになって鳩原さんの好みで自分の身の周りを固めることに幸せを感じるようになって、最終的に、鳩原さんになれると思っていたのか……。
べつに、違うな。
呆れた目を向けてしまう。犬飼は傾げた首を正し口元に笑みを浮かべたので、やっぱりこいつも本気でそんなこと思ってるわけじゃないことがうかがえた。
「あんな人もう他にいない」
常々感じてることだった。鳩原さんと知り合う前の自分が思い出せないくらい今のわたしは鳩原さん一色だった。鳩原さんとの次の約束を胸に生きている人間だった。今日のお出かけが終わったら、次の約束を取り付けないと。ショルダーバッグのヒモを握り締める。春らしい花柄のワンピースは、犬飼のセンスではなく鳩原さんの好みだった。
「そ。まあ、あんまり理想押し付けないようにね」
「押し付けてない」
「押し付けてるよ、二人して」
「…?」
「自分じゃ絶対着ない服じゃんね。やっぱちょいちょい似てるとこあるよな」そう言ってわたしの服を指差した犬飼。一度スカートの裾を見下ろしてから、彼へ不満げな顔を向けてしまう。鳩原さんが選んだという最も価値ある服に向かって、何を。
「そういやおれ、もうちょっとで誕生日だよ」
「そうなんだ」
「冷たいな。他にないの?鳩原ちゃんの誕プレ選ぶの手伝ってあげたじゃん」
「そうだったね」
じゃあ今度何か見繕っておくよ。言って踵を返す。用は済んだ。わたしはこのあと鳩原さんと約束があるんだ。今日は駅近くのお店をぶらぶらするのだ。この服に合うネックレスが欲しいなって思ってるから、見つかれば買いたい。鳩原さんはいつも時間五分前に来てくれるから、わたしも待たせないように行かないと。本部の連絡通路を待ち合わせにしたからここからちょっと時間がかかる。スタスタと無機質な通路を進む。歩きながら考えるのも彼女のことだった。
鳩原未来はわたしにとっての絶滅危惧種みたいなものだった。この世に何人もいない、愛したいと思える人間だった。あんな人もう他にいない。出会えたのは奇跡だ。彼女という人間が消えてしまったらわたしは生きられない。だから消える最後まで一生そばにいたい。絶対ずっと仲良くしてほしい。
「楽しかったね」
「ね。鳩原さんのおかげで可愛いネックレス買えたよ、ありがとう」
「ううん、ちゃんが可愛いの似合うだけだよ」
「ほんと?じゃあ、次遊ぶときつけてくるね」
「うん。次はいつ遊ぼうか」
目を細めて笑う鳩原さん。四月半ばのことだった。
|
|